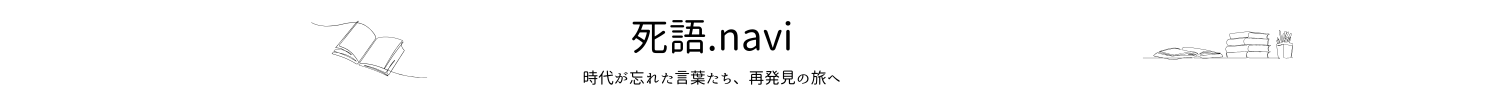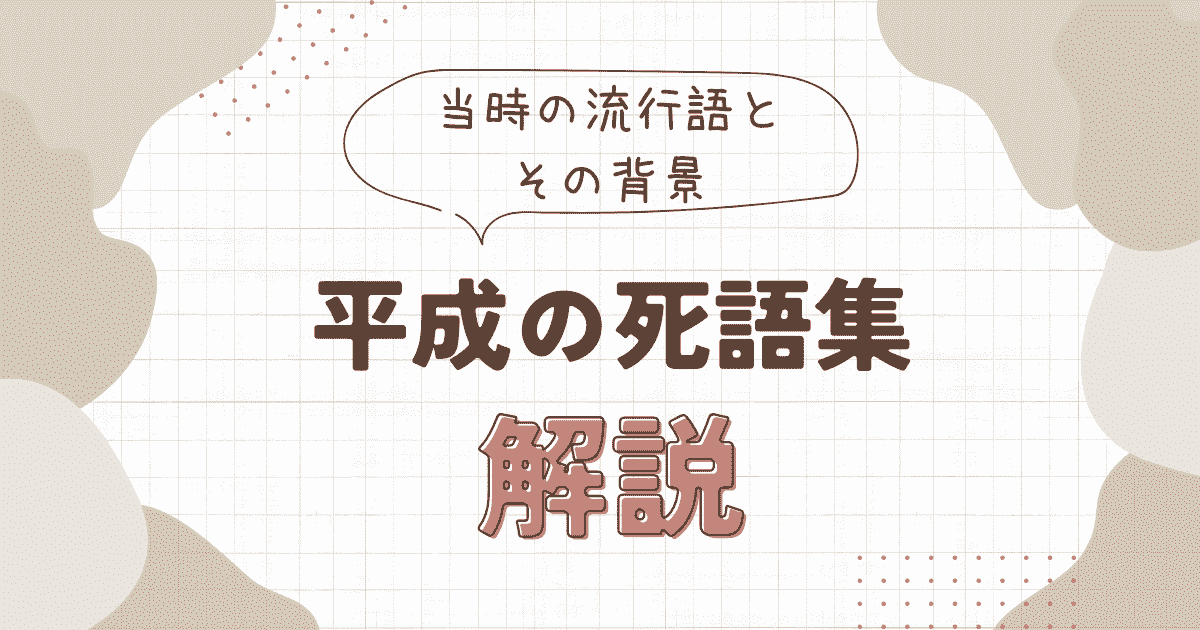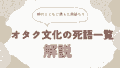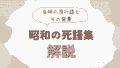平成時代(1989年~2019年)は、日本がバブル崩壊後の変革を迎え、インターネットやSNSが急速に普及した時代でした。
この時期には、テレビ番組や携帯電話、ネット文化の影響を受けた多くの流行語が生まれました。
しかし、新しい言葉が次々と登場する中で、多くの言葉が使われなくなり、「死語」となっていきました。

消えた流行語…こっそりまた使いたいな
本記事では、平成の死語を紹介し、その背景や文化について詳しく解説します。
平成の死語とは?時代とともに消えた言葉

平成時代には、ギャル文化やお笑い番組、ネットスラングなど、さまざまなジャンルから流行語が生まれました。
特に、テレビ番組の影響が強く、芸人の決め台詞やCMのフレーズが一気に流行することもありました。

あの頃の流行語、今も思わず口に出ちゃう!
しかし、インターネットやSNSの普及により、流行語の寿命が短くなり、平成の終わりには使われなくなった言葉も多くあります。
なぜ平成の流行語は死語になったのか?
SNSやネット文化の変化が速いため

平成後半からは、TwitterやInstagram、YouTubeなどのSNSが急速に普及し、新しい言葉が次々と生まれるようになりました。
その結果、言葉の流行サイクルが短くなり、数年で使われなくなる言葉が増えました。
若者の言葉の流行サイクルが短いから

若者を中心に使われる言葉は、次々と新しいものが生み出されるため、古い言葉がすぐに廃れていきます。
例えば、「チョベリバ」(超ベリーバッド)や「バッチグー」(とても良い)は、平成前半に流行しましたが、すぐに使われなくなりました。
メディアやテレビの影響が弱まったから

平成初期から中期までは、テレビ番組やCMの影響で流行語が生まれることが多くありました。
しかし、インターネットの普及により、テレビの影響力が弱まり、SNSや動画配信サービスが主流になったことで、昔ながらの流行語が生まれにくくなりました。
時代背景や価値観の変化により使われなくなった

社会の変化とともに、使われる言葉も変わります。
たとえば、平成初期に流行した「KY」(空気が読めない)は、今ではほとんど使われず、「読めない」や「察しろ」といった表現に置き換えられています。
平成の死語集・代表的な言葉一覧
「チョベリバ」(「超ベリーバッド」の略)

1990年代のギャル語として流行した言葉で、最悪な状況を表す際に使われました。
対義語として「チョベリグ(超ベリーグッド)」もありましたが、どちらも死語となっています。
「ナウい」(今風でおしゃれ)

昭和後期から平成初期にかけて流行した言葉ですが、現在ではほとんど使われず、
「イケてる」や「オシャレ」という言葉に取って代わられています。
「激おこぷんぷん丸」(とても怒っている)

2013年頃に流行した言葉で、「激怒」の強調表現として使われました。
さらに派生した「ムカ着火ファイヤー」などもありましたが、現在ではほぼ使われません。
「KY」(空気が読めない)
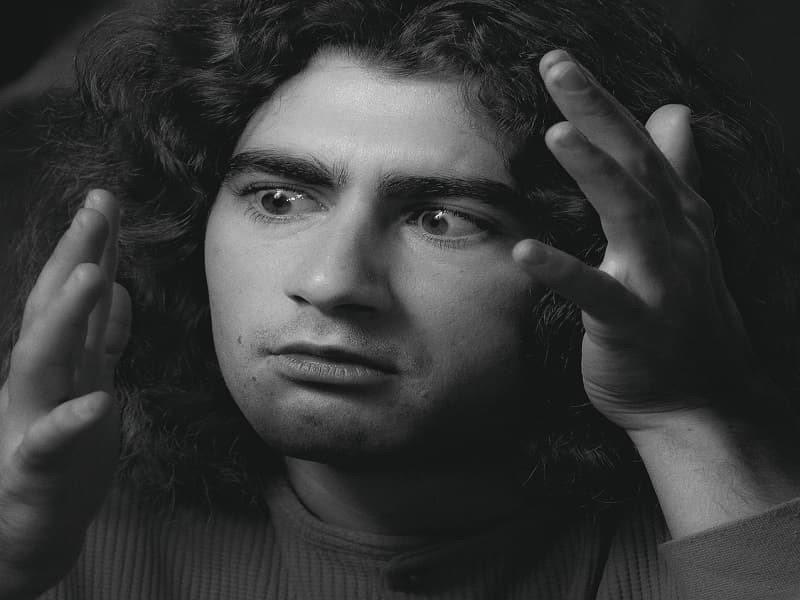
2000年代に流行し、相手の発言や行動が場の空気に合わないときに使われました。
現在では「空気読めてない」と言う方が一般的です。
「バッチグー」(とても良い、完璧)
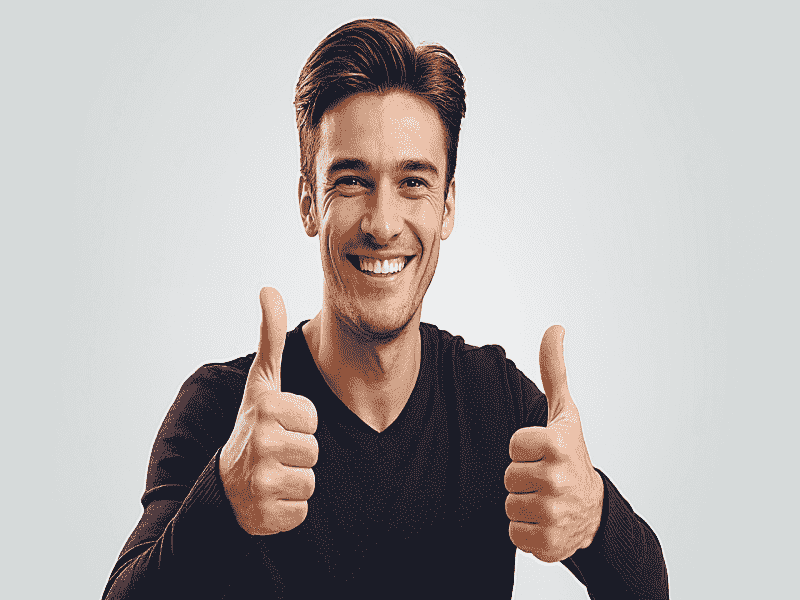
昭和末期から平成初期にかけて流行した言葉で、ポジティブな意味を持ちました。
現在では「完璧」や「最高」といった言葉が使われています。
平成の死語から見る当時の文化と社会
ガラケー時代の独特な略語文化

平成前半はガラケー(フィーチャーフォン)の時代で、文字数を節約するために独特な略語が生まれました。
「KY(空気読めない)」や「orz(落ち込む様子)」などは、当時の携帯メール文化を象徴する言葉でした。
テレビ番組や芸人の流行語が定着

お笑い芸人の決め台詞が流行語になることが多く、例えば「そんなの関係ねぇ!」(小島よしお)や「あたりまえ体操」(COWCOW)などがありました。
ギャル文化の影響を受けた言葉

1990年代から2000年代にかけて、ギャル文化が流行し、「チョベリバ」「アゲアゲ」「マジ卍」などの言葉が生まれました。
しかし、ギャル文化が衰退するとともに、これらの言葉も使われなくなりました。
2ちゃんねる・ネットスラングの流行

平成時代には、ネット掲示板「2ちゃんねる」から生まれたスラングも流行しました。
「ワロタ」「DQN」「リア充」などがその代表例です。
今でも使われる?平成の死語の現代版
「エモい」(平成後期では「感動的」、現在も使われる)

平成後期に流行した「エモい」は、現在でも「感動的」「ノスタルジック」といった意味で使われています。
「それな」(平成では共感の表現、令和でも使われる)
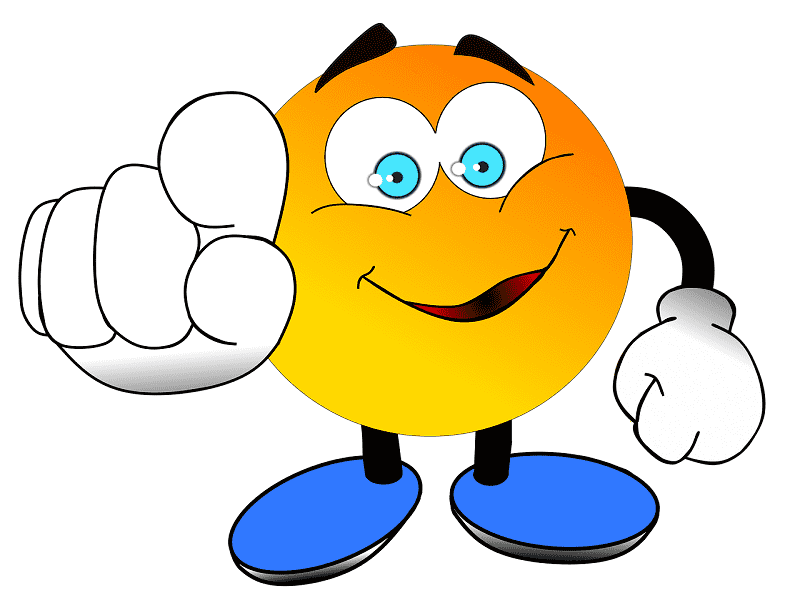
「それな」は平成後期に流行し、現在でも若者の間で広く使われています。
「ガチ」(平成から続くが、意味が少し変化)

「ガチで◯◯」という表現は、現在でも使われていますが、意味が微妙に変化し、日常的な表現として定着しました。
まとめ:平成の死語を学び、日本語の変遷を知る

平成時代の流行語は、テレビやネット文化の影響を受けながら生まれ、時代とともに変化してきました。
多くの言葉が死語となりましたが、一部の言葉は令和になっても使われ続けています。
言葉の移り変わりを知ることで、当時の文化や価値観を振り返ることができ、日本語の進化を感じることができるでしょう。