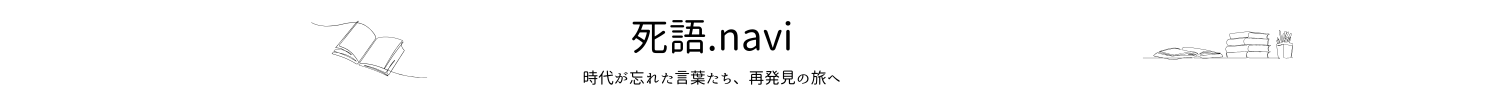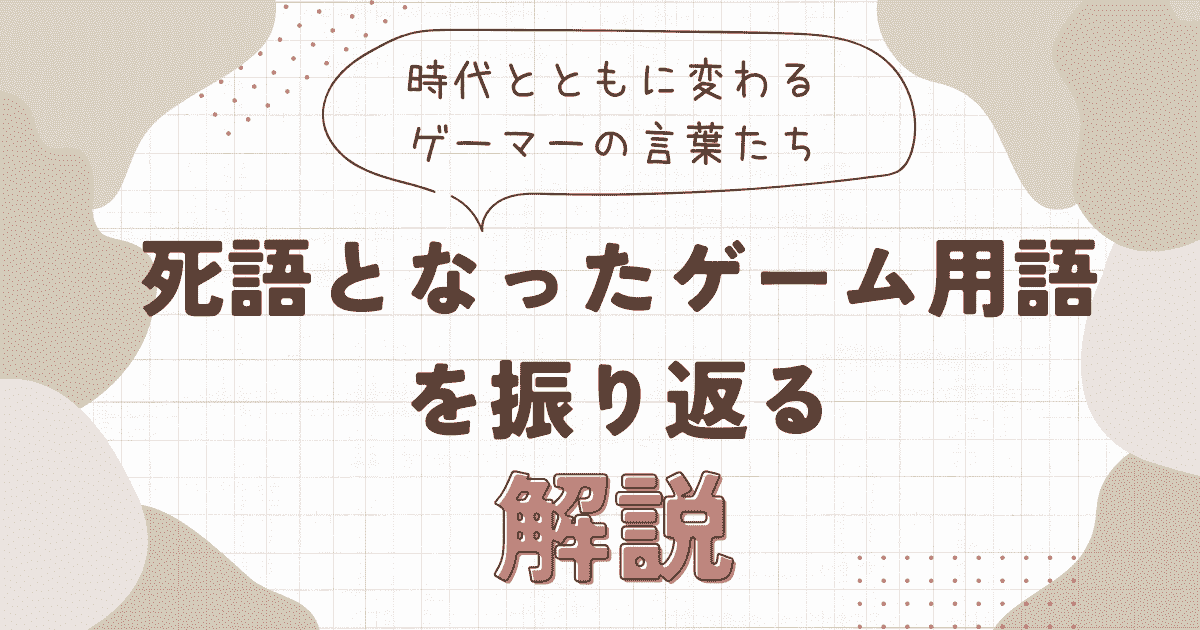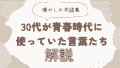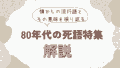ゲーム文化は常に進化し、新たな用語が生まれ、そして消えていきます。
かつて当たり前のように使われていたゲームスラングも、時代の変化とともに姿を消していきました。

あの頃のスラング、いまじゃ誰も使わないね~
本記事では、令和時代にほぼ使われなくなった「死語」となったゲーム用語を振り返り、なぜ消えたのか、その背景を探ります。
また、今もなお生き残っているゲーム用語の特徴についても考察していきます。
懐かしのゲーマー用語を振り返りながら、ゲーム文化の変遷を一緒に見ていきましょう。
死語となったゲーム用語とは?ゲーム文化とともに変わる言葉
ゲーム用語の誕生と流行の流れ

ゲーム用語の多くは、プレイヤーが独自に作り出し、掲示板やSNS、ゲーム内チャットなどを通じて広まります。

ゲー用語、気付けばめちゃくちゃ増えてるな!
例えば、90年代にはアーケードゲーム文化から生まれた「コンボ」「ハメ技」などの言葉がありました。
2000年代に入ると、オンラインゲームの普及とともに「PK(プレイヤーキル)」「BOT(自動操作キャラ)」といったMMORPG発の用語が流行しました。
さらに、2010年代にはFPSやバトルロイヤルゲームの影響で「チーター(不正プレイヤー)」や「キャリー(味方を勝たせる)」といった言葉が定着しました。
世代ごとに変わるゲーマーの言葉

ゲーム用語は、世代ごとに異なる文化を反映しています。
例えば、昭和世代のゲーマーは「残機」「裏技」といった言葉を日常的に使っていましたが、平成世代になると「チート」「バグ技」といった言葉が主流になりました。

ゲーム用語あるある、世代を超えて盛り上がる話題ですね〜
また、令和世代のゲーマーは「GG(Good Game)」「エイム(照準を合わせる)」といった海外発のスラングを日常的に使うようになり、過去のゲーム用語は次第に廃れていきました。
ゲームジャンルによって異なる用語の寿命

ゲーム用語の寿命は、そのジャンルの人気や変化によって異なります。
例えば、アーケードゲーム用語は、ゲームセンターの衰退とともに消えていきました。
一方で、eスポーツの隆盛によってFPSやMOBAの用語は今も広く使われています。
死語となったゲーム用語一覧【令和時代に使われなくなった言葉】
アーケードゲーム時代の死語

・「コンティニュー?」
ゲームオーバー時に表示されるおなじみの言葉だったが、現在はオートセーブ機能の普及でほとんど見かけなくなった。
・「ワンコインクリア」
昔のアーケードゲームでは重要だったが、現在ではゲームの難易度が下がり、あまり使われなくなった。
・「連射機能付きコントローラー」
かつてはシューティングゲームで必須アイテムだったが、今ではボタンを長押しすればOKなゲームが増えた。
コンシューマーゲームで消えた言葉

・「セーブデータ消えた」
昔のゲームではセーブデータが消えることがよくあったが、今ではクラウドセーブが主流になり、ほぼ死語に。
・「ファミコン通信」
ゲーム雑誌『ファミコン通信』(現ファミ通)に由来する言葉だが、雑誌文化の衰退とともに消えていった。
・「ウルテク(ウルトラテクニック)」
攻略本やゲーム雑誌で使われていたが、今は「裏技」や「チート」に置き換わった。
オンラインゲーム黎明期の死語

・「PK(プレイヤーキル)」
MMORPGではよく使われたが、最近は「PvP」の方が一般的になった。
・「BOT(ボット)」
自動操作するキャラクターのことを指したが、今では「AI」「チート」のほうが一般的に使われる。
・「ネカマ」
ネットゲームで男性が女性キャラを使うことを指したが、今では「Vtuber」などの新しい文化に取って代わられた。
スマホゲームの初期に流行したが消えた表現

・「リセマラ」
かつてはスマホゲームの定番だったが、最近では確定ガチャや引き直し機能が増え、重要度が低くなった。
・「スタミナ回復待ち」
昔のソシャゲではよく使われたが、最近はスタミナ制を撤廃するゲームも増えてきた。
・「ガチャ爆死」
現在も使われることはあるが、「沼る」「引き弱」などの新しい表現が登場し、あまり聞かなくなった。
まとめ:死語となったゲーム用語とこれからのゲーマー文化

ゲーム文化の進化とともに、過去の言葉が消え、新たなスラングが生まれ続けています。
令和のゲーマーは、過去の用語を知らないことも多く、世代間のギャップが生じることもあります。
しかし、ゲームが続く限り、新しい言葉は生まれ、定着するものもあれば、消えていくものもあります。
今後も、ゲーマー文化の進化とともに、新たなゲーム用語が登場することでしょう。