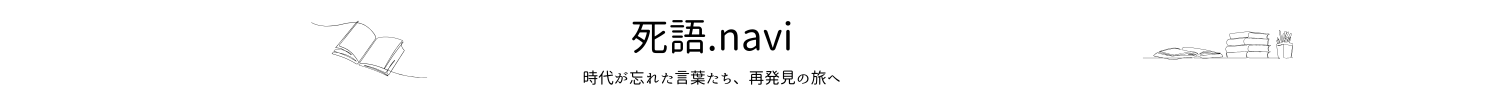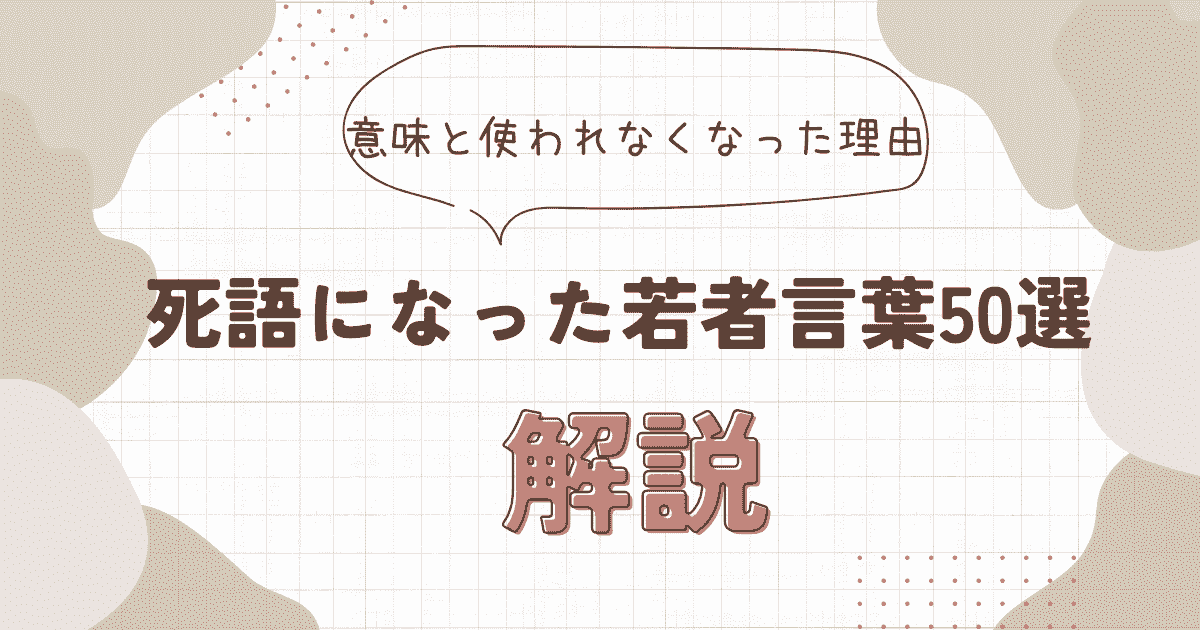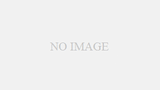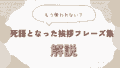若者言葉は時代とともに生まれ、そして消えていきます。
一世を風靡した言葉でも、気がつけば誰も使わなくなり、「死語」と呼ばれるようになります。
特に流行語やスラングは、短期間で広まり、あっという間に廃れてしまうことが少なくありません。

流行語、気づけば死語。言葉の儚さよ。
本記事では、かつて流行したものの今ではほとんど使われなくなった若者言葉を紹介し、その意味や由来を解説します。
また、若者言葉がなぜ死語になるのか、その背景についても考察します。
死語になった若者言葉とは?

「死語になった若者言葉」とは、一時的に流行したものの、現在ではほとんど使われなくなった言葉のことです。
こうした言葉は、特定の年代の若者の間で広まり、その時代を象徴するものとなりますが、流行が終わるとともに次第に使われなくなります。
なぜ若者言葉は死語になるのか?
流行の移り変わりが早いから

若者文化は常に変化しており、新しい流行が次々と生まれます。
そのため、一時的に流行した言葉もすぐに古くなり、使われなくなってしまいます。
特にファッションや音楽と密接に関係する言葉は、そのトレンドとともに消えていくことが多いです。
インターネットやSNSの影響で新語が次々生まれるから

近年、インターネットやSNSの普及により、新しい言葉が驚くべきスピードで生まれています。
特にTwitterやTikTok、YouTubeなどのプラットフォームでは、短期間で流行語が広まり、
すぐに新しい言葉に取って代わられます。
世代によって言葉の感覚が変わるから

若者言葉は特定の世代でのみ通じることが多く、次の世代には伝わりにくいものです。
新しい世代の若者は、過去の流行語を「古臭い」と感じることが多く、自然と使われなくなります。
メディアや芸能界の影響でブームが短命になりやすいから

テレビや雑誌、芸能界で流行した言葉は、一気に広まるものの、その分短命になりやすい傾向があります。
特にバラエティ番組やドラマで使われたフレーズは、一時的に人気を博すものの、番組が終わるとともに廃れてしまうことが多いです。
かつて流行した死語になった若者言葉50選

・ナウい
1970〜1980年代に流行した言葉で、
「今」を意味する英語の「Now」に日本語の形容詞「〜い」をつけた造語です。
当時はファッションやライフスタイルが「ナウい」かどうかが話題になり、テレビや雑誌でも頻繁に使われました。
・バイビー
「バイバイ」と「ベイビー(Baby)」を組み合わせた可愛らしい別れの挨拶です。
1970〜1980年代にかけて流行し、特に女性の間でよく使われました。
・ださい
「ださい」は、元々1960年代ごろから使われていた言葉で、センスが悪い、かっこ悪いという意味を持ちます。
・チャラい
1980年代後半から1990年代にかけて流行した言葉で、遊び人っぽい軽薄な態度や服装の人を指します。
「チャラチャラしている」から派生した言葉だと言われています。
・アッシー
バブル時代(1980〜1990年代)に流行した言葉で、女性を車で送り迎えをするだけの男性を指します。「
足(車)を提供する人」という意味から、「アッシー君」とも呼ばれました。
・メッシー
アッシーと同じくバブル時代に登場した言葉で、食事(メシ)を奢ってくれる男性を指します。
特に高級レストランなどで女性に奢る男性を「メッシー君」と呼んでいました。
・ ミーハー
「ミーハー」は、流行や有名人に熱中する人を指す言葉で、昭和時代から使われていました。
語源には諸説ありますが、戦前の新聞小説に登場した「みいちゃん・はあちゃん(ミーハー)」という言葉が由来とされています。
8. ジャンケンポンずっこ
ジャンケンの勝負で負けた人を指す言葉で、昭和時代に子どもたちの間で広まりました。
「ずっこける」や「ずるい」といったニュアンスを含んでいます。
・チョベリバ
1990年代後半に女子高生の間で流行した「ギャル語」の一つで、
「超(ちょ)」「ベリー(very)」「バッド(bad)」を組み合わせた言葉。
「最悪」という意味で使われました。
・チョベリグ
「チョベリバ」と対になる言葉で、
「超(ちょ)」「ベリー(very)」「グッド(good)」を組み合わせた表現。
「最高」「とても良い」という意味で使われました。
・バッチグー
「バッチリ」と「グー(good)」を組み合わせた言葉で、1980年代〜1990年代にかけて流行しました。
特にバラエティ番組などで頻繁に使われました。
・ MK5
1990年代後半に女子高生の間で流行した略語で、「マジでキレる5秒前」の頭文字をとったもの。
怒りが頂点に達しそうなときに使われました。
・ガビーン
漫画の擬音語として登場し、1970〜80年代に若者の間で広まりました。
ショックを受けたときのリアクションとして使われました。
・だっちゅーの
1998年頃にお笑いコンビ「パイレーツ」が使っていた決めゼリフ。
胸の前で手をクロスさせるポーズとともに一世を風靡しました。
・よっちゃんイカ
駄菓子の「よっちゃんイカ」に由来する言葉で、元気で活発な人を指すときに使われました。
特に子供や若者の間で親しみを込めて使われていました。
・ぶっ飛び
1980〜1990年代に流行した言葉で、「驚く」「とてもすごい」という意味で使われました。
・キモい
1990年代後半に登場し、「気持ち悪い」を省略した形のスラングです。
・パラパラ
1990年代後半から2000年代初頭にかけて流行したダンススタイルで、
特にギャルやギャル男の間で人気がありました。
ユーロビートに合わせて手を素早く動かす独特のダンスが特徴です。
・キボンヌ
2000年代初頭にインターネット掲示板「2ちゃんねる(現・5ちゃんねる)」で生まれたネットスラング。
「希望する」をもじった言葉で、「○○キボンヌ(○○が欲しい)」のように使われました。
・逝ってよし
1990年代後半〜2000年代初頭にかけて、「2ちゃんねる」で使われたネットスラング。
相手を強く否定するときに「お前はもう逝ってよし」といった形で使われました。
・乙
ネット掲示板を中心に広まった言葉で、「お疲れ様です」を省略した表現。
「○○乙」といった形で使われ、誰かの努力をねぎらう際に用いられました。
・うp
「アップロード」の略語で、特に画像や動画をネットに投稿する際に「うpする(アップする)」と表現されていました。
・メンゴ
「ごめん」をくだけた言い方にした言葉で、昭和時代から使われていました。
特に1980〜1990年代には若者の間で流行し、「メンゴメンゴ」と繰り返すことで軽い謝罪のニュアンスを表しました。
・ 激おこ
2013年ごろに流行したネットスラングで、「激しく怒っている」ことを表します。
元々は「激おこぷんぷん丸」というフレーズが話題になり、その略称として「激おこ」が広まりました。
・それな
2010年代に若者の間で流行した言葉で、「それは本当にそう」「同意」という意味で使われました。
会話の中で相手の意見に強く賛同するときに「それな」と短く返すのが特徴でした。
・ガチで
2000年代後半から若者の間で広まったスラングで、「本気で」「真剣に」という意味。
「ガチ勢(真剣に取り組む人)」という言葉も派生しました。
・イミフ
「意味不明」の略語として2000年代に流行しました。
「イミフすぎる」「イミフなんだけど」といった形で使われ、ネットや若者の会話の中で広まりました。
・ なう
2010年代初頭にTwitterを中心に流行した言葉で、「○○なう」といった形で今していることを表現するのが特徴でした。
「カフェなう」「渋谷なう」などのフレーズが一世を風靡しました。
・ぴえん
2019年頃に若者の間で流行した言葉で、「悲しい」「切ない」「寂しい」といった感情を表現する際に使われました。
SNS上では「ぴえん🥺」という顔文字とセットで使われることが多く、特に10代の女性の間で広まりました。
・マジ卍
2017〜2018年頃にギャルの間で流行した言葉で、はっきりとした意味はなく、
ノリやテンションが高まったときに使われました。
「マジでヤバい」「最高」といったポジティブな意味合いで使われることが多かったです。
・ンゴ
元々はアメリカの野球選手「フェルナンド・ロドニー」のミスを揶揄する「Rodney Ngogogogogo」というスレッドが発祥。
日本のネット掲示板で短縮され、「ンゴ」が語尾につくスラングとして広まりました。
・よき
「良き」という言葉を若者向けに略した表現で、「これよき!」「よきよき!」のように使われました。
2010年代後半から2020年頃にかけて流行し、特に女性の間でよく使われました。
・ 草
「笑」のインターネットスラングで、「w」の形が草が生えているように見えることから「草」と表現されるようになりました。
「大草原不可避(めちゃくちゃ笑った)」といった派生語も誕生しました。
・それなー
「それな」をさらに伸ばした形の言葉で、2010年代後半に若者の間で流行しました。
相手の意見に強く同意するときに「それなー!」と使われました。
・KP
「乾杯(かんぱい)」を略した言葉で、2010年代後半から飲み会の場で若者が使うようになりました。
特に女子会やSNS投稿の際に「KP〜!」とコメントするのが流行しました。
・やばたにえん
「やばい」に老舗のお茶漬けメーカー「永谷園(ながたにえん)」の語感をかけた造語で、
「とてもやばい」という意味で使われました。
2010年代後半に女子高生の間で流行しました。
・ふぁぼる
Twitterの「Favorite(お気に入り)」ボタンを押すことを指す言葉で、
「ふぁぼる」「ふぁぼって!」などの形で使われていました。
2010年代初頭にTwitterの普及とともに流行しました。
・バイブス
英語の「vibes(vibrations=波動、雰囲気)」を日本語風にアレンジした言葉で、
「バイブス上がる!(テンションが上がる)」「バイブスいいね!(雰囲気が良い)」などの形で使われました。
・シースー
「寿司」を逆さ読みにした隠語のような表現で、1990年代〜2000年代初頭に流行しました。
特にバブル時代のサラリーマンやギャルの間で使われることが多く、
「シースー行こうぜ!(寿司を食べに行こう)」といった形で使われました。
・イケメソ
「イケメン」と「メソメソ(泣く)」を組み合わせた言葉で、「泣いているけれどイケメンな人」という意味で使われました。
2000年代のネット掲示板やSNS上で流行し、「○○メソ」といった派生語も誕生しました。
・だもんで
主に東海地方の方言として使われていた言葉で、「だから」「そういうわけで」といった意味を持ちます。
・ウケる
「面白い」「笑える」という意味で1990年代〜2000年代に流行した言葉。
会話の中で「それウケる!」といった形で使われました。
43. チョロい
「簡単」「すぐにできる」という意味で使われるスラングで、元々は1980年代から使われていた言葉。
2000年代以降は、「チョロすぎる」「チョロい相手」などの形で若者の間でも使われました。
・どゆこと
2000年代に流行した若者言葉で、「どういうこと?」を略したもの。
驚いたときや理解が追いつかないときに「え、どゆこと?」といった形で使われました。
・まじ卍
2017年頃にギャル語として流行した言葉。
「卍」自体には特に意味はなく、ノリや勢いを表すために使われました。「まじ卍〜!」と叫ぶことで、テンションの高さを示しました。
・わんちゃん
「ワンチャンス(one chance)」の略で、「もしかしたら成功するかも」「可能性があるかも」といった意味で使われました。
・ぱない
「半端ない」を略した形で、関西弁由来の言葉。
特にスポーツ界では「大迫半端ない」というフレーズとともに話題になりました。
・しょんどい
「しんどい」と「どい(重い)」を組み合わせたような言葉で、関西圏を中心に若者の間で使われていました。
「今日はバイトしょんどいわ〜」といった形で使われました。
・ワロタ
「笑った」を崩したネットスラングで、主に2ちゃんねる(現・5ちゃんねる)などの掲示板文化から生まれました。
「クソワロタ」「大草原不可避」などの派生語も登場しました。
・くそワロタ
「ワロタ」の強調版で、「めちゃくちゃ笑った」「爆笑した」という意味。
2000年代後半からネットスラングとして広まりました。
現代の若者言葉もいずれは死語になる?
現在の流行語も短命なものが多い

近年の流行語は、そのほとんどが短期間で消えていきます。
特にSNSを中心に流行する言葉は、急速に広まる一方で、飽きられるのも早いのが特徴です。
SNSや動画配信で新しい言葉が生まれ続ける

インターネット、特にSNSや動画配信サービスの普及によって、新しい言葉が次々と生まれています。
TikTokやYouTubeのショート動画などは、短期間で爆発的に拡散するため、
流行語のサイクルがさらに加速しています。
一部の言葉は定着し、一般語になることもある

すべての若者言葉が消えていくわけではなく、一部の言葉は一般的な言葉として定着することもあります。
例えば、「ダサい」「イケてる」「ウザい」などは、元々は若者言葉でしたが、
現在では幅広い世代に使われる一般的な日本語となっています。
このように、流行語の中でも使い勝手が良く、意味がわかりやすいものは、時代を超えて生き残る可能性があります。
まとめ:死語になった若者言葉の意味と使われなくなった理由

若者言葉は一時的なブームとして広まりますが、新しい言葉が生まれることで自然と使われなくなります。
また、現代の若者言葉も同じ運命をたどる可能性が高く、数年後には今流行している言葉も死語になっているかもしれません。
しかし、一部の言葉は一般的な日本語として定着し、長く使われ続けることもあります。
言葉の流行は常に変化し続けています。
今使っている若者言葉も、いずれは「懐かしい」と言われる日が来るでしょう。