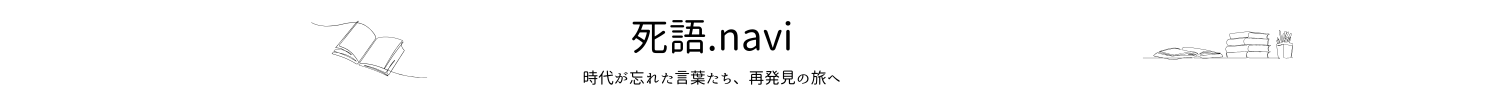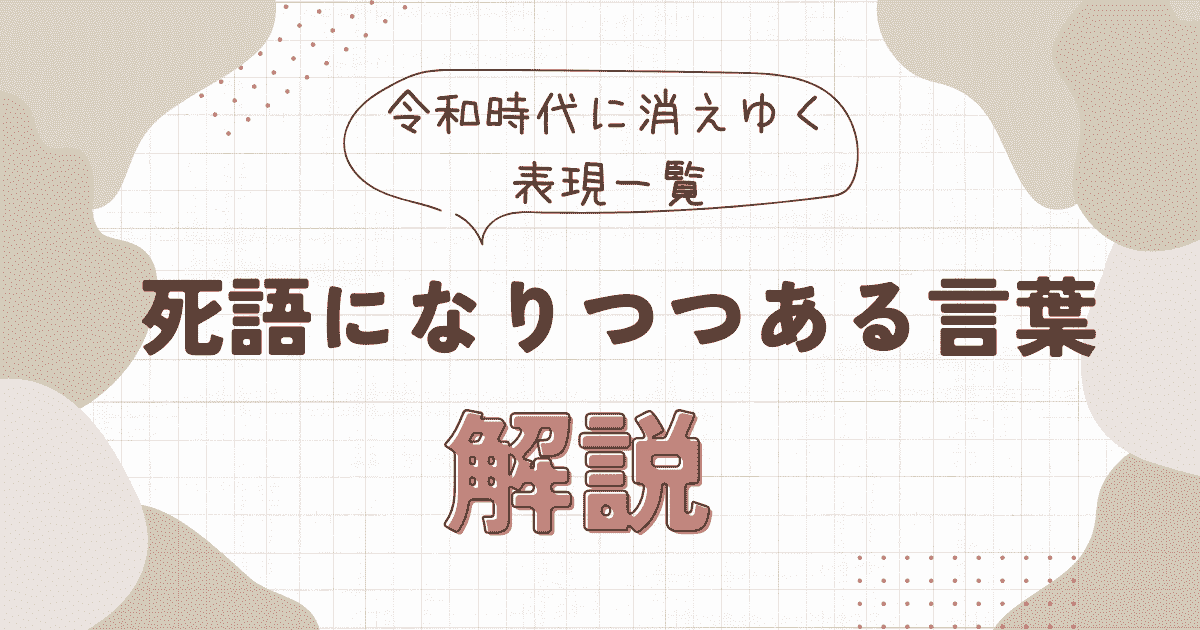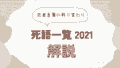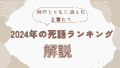言葉は時代とともに変化し、新しい表現が生まれる一方で、かつて流行した言葉が「死語」となって消えていきます。
特に若者言葉や流行語は短命であり、数年で使われなくなることも少なくありません。

言葉の儚さ、ちょっと切ないよね。
本記事では、令和時代に消えつつある言葉を一覧で紹介しながら、
言葉が死語になる理由や、長く使われ続ける言葉の特徴について詳しく解説します。
昭和、平成、そして令和へと時代が移り変わる中で、
どのような言葉が消え、どのような言葉が生き残ったのかを探っていきましょう。
死語になりつつある言葉とは?時代とともに変わる言葉の流れ
死語とはどのような言葉か?

死語とは、「日常会話の中でほとんど使われなくなった言葉」を指します。
ただし、完全に消えるわけではなく、一部の人々が懐かしんで使うこともあります。

死語でも、懐かしさがたまらないよね。
例えば、昭和時代に流行した「ナウい(今風の)」や「アベック(カップル)」、
平成の「チョベリバ(超ベリーバッド)」といった表現は、現在ではほぼ使われません。
このように、時代とともに使われなくなった言葉が「死語」と呼ばれます。
流行語と死語の違い

流行語と死語は密接に関係していますが、明確な違いがあります。
流行語
一時的に多くの人々の間で使われるようになった言葉のことです。
流行語の中には、そのまま日常会話に定着して長く使われるものもあれば、すぐに廃れるものもあります。
死語
かつて流行した言葉のうち、現代ではほとんど使われなくなったものを指します。
つまり、流行語が一定期間を経て死語になるという流れがあるのです。
どのような言葉が死語になりやすいのか?

死語になりやすい言葉には、いくつかの共通点があります。
1. 一時的なブームに乗った言葉
その時代の流行に強く依存していた言葉は、ブームが終わると同時に急速に廃れていきます。
2. 若者言葉やスラング
若者が使う言葉は移り変わりが激しく、次の世代には通じなくなることが多いです。
3. 技術や文化の変化による影響
例えば、「ポケベルが鳴る」は、ポケットベルが一般的だった時代の表現ですが、今ではほとんど使われません。
なぜ言葉は死語になるのか?令和時代の言葉の移り変わり
SNSやネット文化の影響

近年では、TwitterやTikTokなどのSNSの普及により、新しい言葉が急速に生まれ、広まり、そして消えていくサイクルが加速しています。
例えば、「エモい」「ぴえん」はSNSで流行しましたが、現在ではすでに「古い」と言われることもあります。特にネットスラングは流行が短命で、数年で使われなくなることが多いです。
メディアの変化による言葉の流行の変遷

かつてはテレビ番組や雑誌が流行語を生み出していましたが、現代ではSNSが主流になり、テレビ発の流行語は減少しています。
例えば、「そんなの関係ねぇ!(小島よしお)」や「ゲッツ!(ダンディ坂野)」のようなギャグは、テレビの影響が強かった時代ならではの流行語でしたが、現在ではほぼ使われていません。
価値観やライフスタイルの変化

社会の価値観が変化すると、過去に普通に使われていた言葉が不適切とされることもあります。
例えば、「オカマ」や「ホモ」という言葉は、現在では差別的な表現とみなされることが増えました。
死語になりつつある言葉一覧【令和時代に消えゆく表現】
若者の間で使われなくなった言葉

・「あげみざわ」
「テンションが上がる」の意味で使われていましたが、現在ではほぼ消滅しました。
・「バイブス」
「雰囲気」「ノリ」の意味で使われていましたが、最近では「フィーリング」に置き換えられつつあります。
ネットスラングの衰退

・「ワロタ」
かつて2ちゃんねるなどで頻繁に使われていましたが、「草」に取って代わられました。
・「orz」
ガックリと肩を落とす絵文字的表現ですが、現在はほぼ使われません。
テレビ発の流行語の消滅

・「ナウい」
「今風の」という意味の言葉ですが、今ではほぼ聞かれません。
・「バッチグー」
「とても良い」という意味でしたが、完全に死語となりました。
まとめ:死語になりつつある言葉と令和時代の新しい表現

言葉は時代とともに変化し、新しい表現が生まれる一方で、かつての流行語は次第に使われなくなります。
特にSNSの影響が強い令和時代では、言葉の流行サイクルがさらに短くなっています。
しかし、言葉の変化は文化の進化を反映するものでもあります。
これからも新しい言葉が生まれ、消えていく流れは続くでしょう。