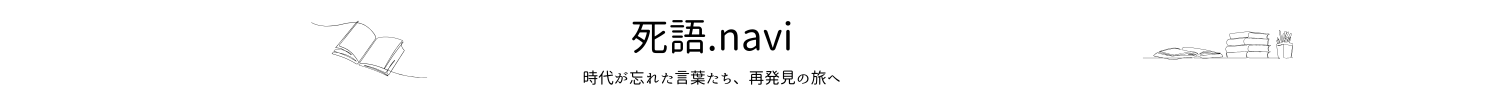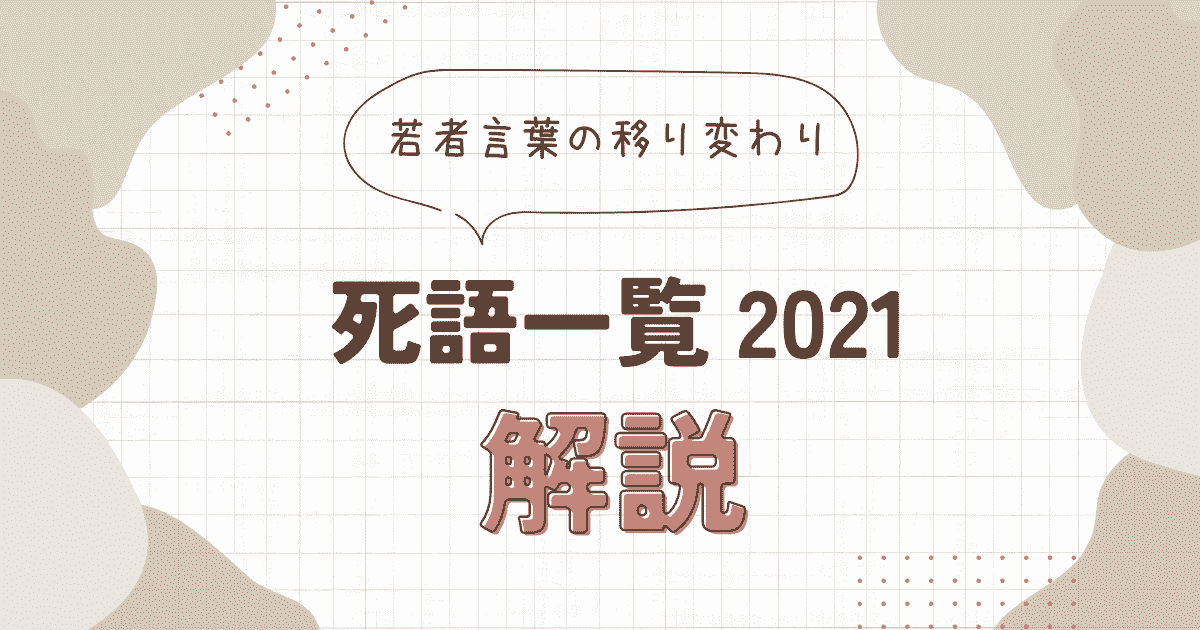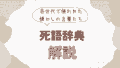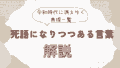言葉は時代とともに変化し、特に若者言葉は流行が激しく移り変わります。
2021年にもさまざまな若者言葉が生まれましたが、その多くは短期間で使われなくなり、「死語」となってしまいました。

「気づけばもう死語…移り変わり早すぎ!」
本記事では、2021年に流行した若者言葉や、なぜそれらがすぐに死語になってしまうのかを解説します。
若者言葉の特徴を知ることで、言葉の移り変わりや流行のメカニズムを理解できるでしょう。
2021年の若者言葉と死語の定義
若者言葉とは何か?

若者言葉とは、主に10代から20代の若者の間で流行する特有の言葉や表現を指します。
SNSや動画配信サイト、ネットスラングなどの影響を強く受け、短縮されたり、独特の言い回しが生まれたりします。
また、若者言葉は「共感」や「ノリ」を重視する傾向があり、特定の感情をシンプルに伝えることが特徴です。

ノリと勢いで作られる若者言葉、あなどれない!
たとえば、「きゅんです」はときめく気持ちを、「ぴえん」は悲しい気持ちを表す言葉として人気を集めました。
死語とはどのような言葉か?

死語とは、かつて流行したものの、現在ではほとんど使われなくなった言葉を指します。
特に若者言葉は流行の移り変わりが早いため、数年経つと使われなくなるケースが多いです。

気づけば通じないワード多すぎ問題!
例えば、1990年代に流行した「チョベリグ(超ベリーグッド)」や「チョベリバ(超ベリーバッド)」は、当時の若者の間で広まりましたが、現在ではほとんど聞かれなくなりました。
同様に、2021年の若者言葉もいずれ死語になってしまう運命にあります。
2021年に流行した若者言葉の例

2021年には、多くの若者言葉がSNSを中心に流行しました。
以下はその代表的な例です。
- 「ぴえん」…悲しみや切なさを表現する言葉。
- 「きゅんです」…胸がときめく様子を表現する。
- 「〇〇しか勝たん」…特定のものを絶賛するときに使う。
- 「秒で」…「すぐに」や「瞬時に」という意味。
これらの言葉はTikTokやTwitterなどのSNSで広まり、若者の間で日常的に使われるようになりました。
しかし、流行の移り変わりが激しいため、数年後には死語となる可能性も高いです。
なぜ若者言葉はすぐに死語になるのか?
流行の移り変わりが早いから
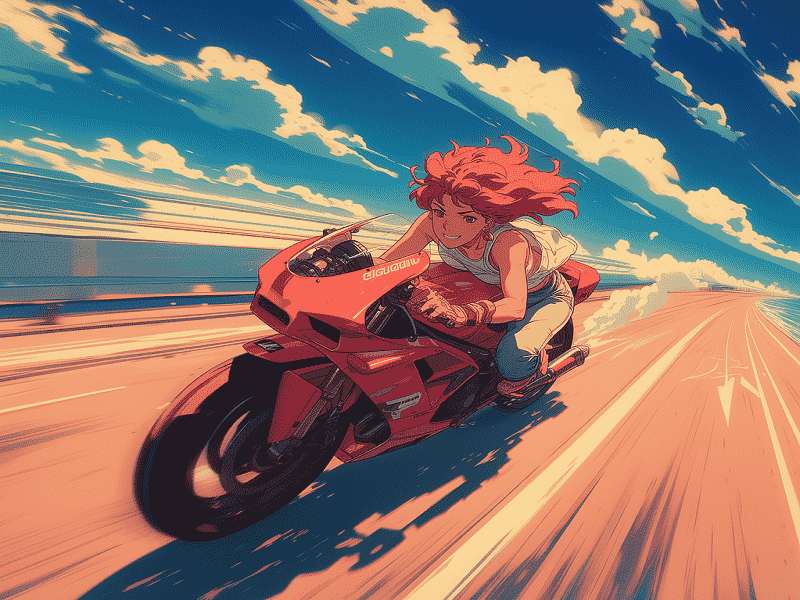
若者文化は常に新しいものを求める傾向があり、言葉の流行も短期間で変化します。
ファッションや音楽と同じように、言葉のトレンドも一定期間が過ぎると「古い」とみなされるため、若者言葉はすぐに廃れてしまいます。
SNSの影響で一気に広まりすぐ廃れるから

TwitterやTikTok、InstagramなどのSNSの普及により、新しい言葉が一気に拡散されるようになりました。
しかし、短期間で広まる一方で、飽きられるのも早く、ブームが去るとすぐに使われなくなる傾向があります。

あっという間に消える言葉、多すぎ!
たとえば、「ぴえん」は2020年から2021年にかけて人気を博しましたが、
2022年には「もう古い」とされ、若者の間での使用頻度が激減しました。
新しい言葉が次々に生まれるから

若者の間では、常に新しい言葉が生まれています。
特にネットスラングの影響を受けた言葉は、短期間で流行し、次の新語に取って代わられることが多いです。
例えば、「それな」という言葉は一時期流行しましたが、現在では「わかる」や「ガチ」など、別の言葉に置き換えられつつあります。

どんどん言葉が変わってくから追いつけないわ!
このように、新しい言葉が次々と登場することで、過去の言葉が使われなくなり、死語となっていきます。
一部の世代でしか使われないから

若者言葉の多くは特定の世代にしか使われません。
そのため、使う人が年齢を重ねると自然に使われなくなり、次の世代には受け継がれずに消えてしまうのです。
例えば、「チョベリグ」や「ナウい」といった言葉は、90年代に流行しましたが、現在の若者はほとんど使いません。

あの頃は「チョベリグ」で盛り上がったよね
同様に、2021年に流行した言葉も、数年後にはほとんど聞かれなくなる可能性が高いです。
2021年時点で「死語」となった若者言葉一覧
「あげみざわ」

「テンションが上がる」という意味で使われていた言葉です。
「あげみ(テンションが上がる)」と、語尾に「みざわ」をつけた造語で、2018~2019年頃に流行しました。
しかし、2021年にはほとんど使われなくなり、死語となりました。
「それな」
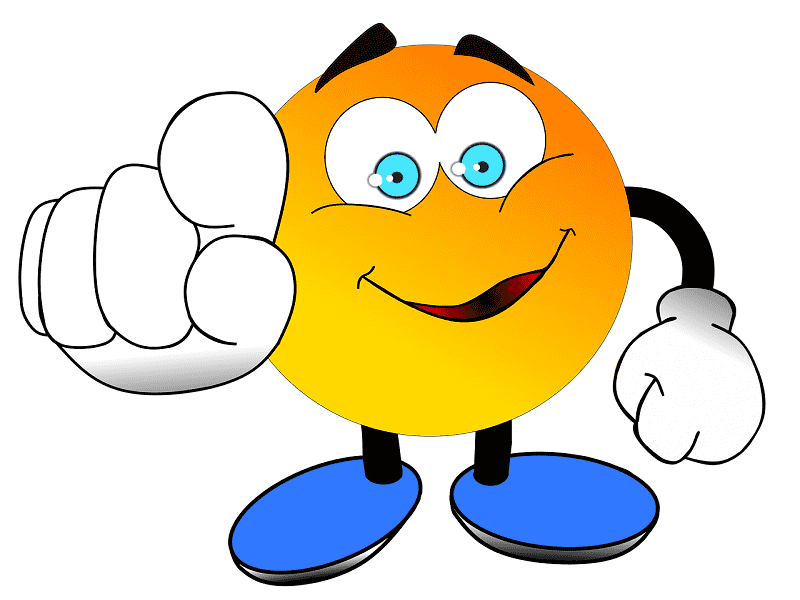
相手の意見に強く同意する際に使われていた言葉です。
「わかる」「共感する」という意味で使われましたが、シンプルすぎるためか、
次第に「わかる」「ガチ」など別の表現に取って代わられ、2021年には使われなくなりました。
「よき」

「良い」を崩した表現で、「いいね」「OK」という意味合いで使われていました。
しかし、言葉としてのインパクトが薄れ、新しい言葉に押される形で2021年にはほとんど見られなくなりました。
「バイブス」

「雰囲気」や「ノリ」を意味するスラングで、「バイブスが高い」「バイブス上げていこう」などのフレーズで使われていました。
しかし、カジュアルな言葉の入れ替わりが激しい若者文化の中で徐々に廃れ、2021年には死語扱いされるようになりました。
「チョベリグ・チョベリバ」

1990年代に流行した「超ベリーグッド(チョベリグ)」と「超ベリーバッド(チョベリバ)」という言葉ですが、若者言葉の移り変わりの象徴とも言えるほど完全に死語化しました。
2021年の若者の間ではほとんど使われていません。
昔の若者言葉と2021年のトレンドの違い
ネットスラングの影響が強くなった

かつての若者言葉は、日常会話やテレビ番組などをきっかけに生まれることが多かったですが、
2021年時点ではSNSやネット掲示板発の言葉が主流になっています。
例えば、「ぴえん」や「〇〇しか勝たん」などの言葉は、TwitterやTikTokを通じて爆発的に広まりました。
短縮形の言葉が増えた
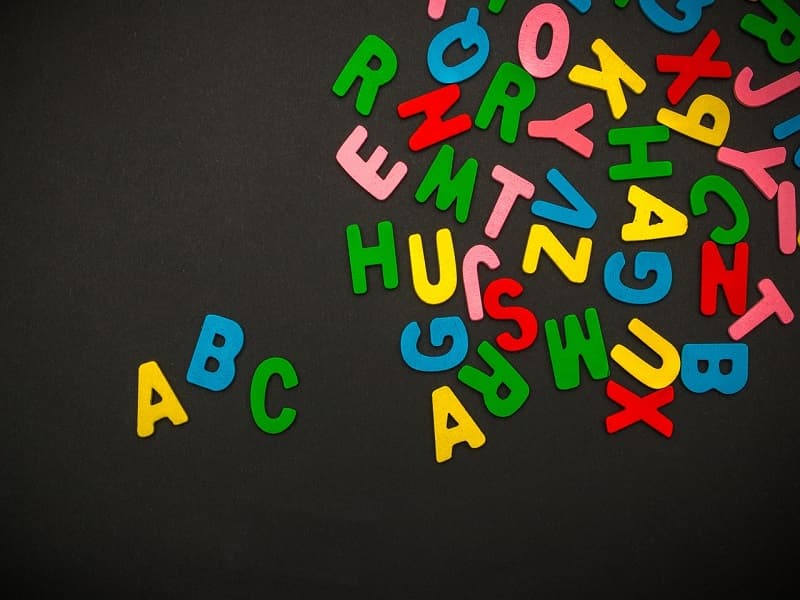
言葉を短縮する文化は昔からありましたが、近年ではよりシンプルな形が好まれる傾向にあります。
「バイブス」を「バブみ」と言い換えたり、「マジでヤバい」を「マ?(マジ?)」と略すなど、より短いフレーズで感情を表す言葉が増えています。
映像コンテンツ発の言葉が増加

YouTubeやTikTokの普及により、動画コンテンツから生まれる若者言葉が増えています。
たとえば、「きゅんです」はTikTokの流行から広まり、「ガチ勢・エンジョイ勢」はゲーム実況文化から派生した言葉です。
映像コンテンツの影響力が増したことで、言葉の広がり方も大きく変化しました。
語尾を変化させる言葉が減った

昔の若者言葉には、「~ざます」「~でしゅ」など、語尾を変化させる言葉がよく見られました。
しかし、2021年の若者言葉では、語尾の変化よりも単語自体の短縮やネットスラングの流用が主流になっています。
そのため、「~み」「~ぴ」などの語尾変化はあるものの、昔ほどの流行は見られなくなりました。
2021年以降に消えつつある若者言葉とは?
「ぴえん」

「泣きたいほど悲しい」という意味で使われた「ぴえん」ですが、2022年以降はあまり使われなくなりました。
代わりに「ぴえん超えてぱおん」などのバリエーションが一時期登場しましたが、結局どれも短命に終わっています。
「きゅんです」
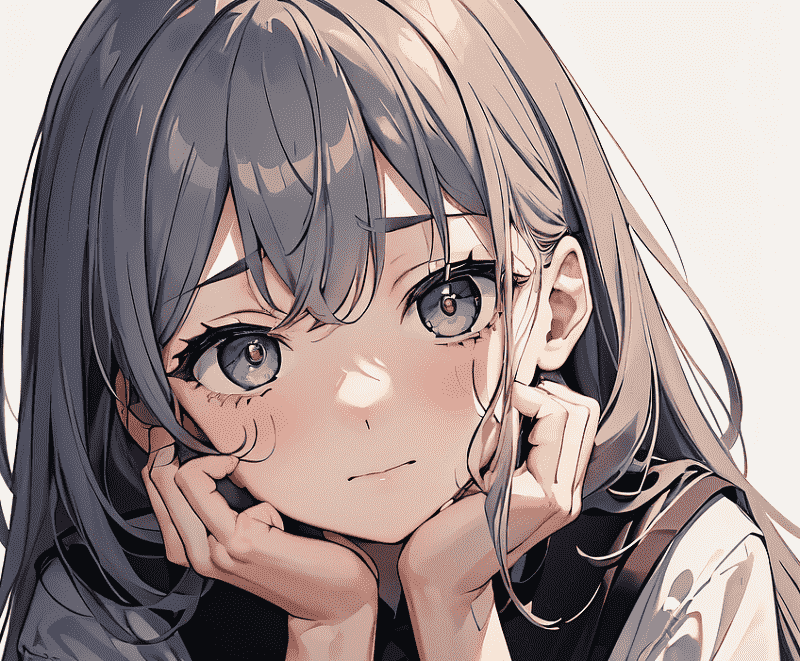
胸がときめく様子を表す「きゅんです」は、TikTokの流行とともに広まりました。
しかし、2022年以降は使用される頻度が減少し、すでに「古い」と言われ始めています。
「〇〇しか勝たん」

「〇〇が一番好き」「〇〇が最高」という意味で使われた言葉ですが、
あまりに多用されすぎたことで飽きられ、次第に使われなくなりました。
「ガチ勢・エンジョイ勢」

ゲームや趣味のスタンスを表す言葉ですが、2021年以降は「ガチ勢」という言葉が少し古いと感じられるようになり、代わりに「エンジョイ勢」よりも「エンジョイ勢寄り」などの柔らかい表現が増えてきました。
「秒で」

「すぐに」「瞬時に」という意味の「秒で」は、シンプルで使いやすい言葉でしたが、
徐々に「即」「ガチで」などの別の表現が使われるようになり、2021年以降は少しずつ使われなくなっています。
死語にならず定着した若者言葉の特徴
幅広い世代に使われている

若者言葉の中には、特定の年代に限定されず、幅広い年齢層に浸透したことで定着するものがあります。
例えば、「微妙」や「ノリ」「マジ」などの言葉は、もともと若者の間で使われていた表現でしたが、現在では中高年層にも浸透し、一般的な日本語として定着しました。

すっかり世代を超えて定着した感じだね。
世代を超えて使われる言葉は、会話の中で自然に使われる機会が増えるため、長く生き残る傾向があります。
日常会話で使いやすい

日常会話の中で頻繁に使われる言葉は、流行が終わった後も定着しやすいです。
例えば、「めっちゃ」や「ヤバい」は、もともと若者言葉でしたが、使いやすさから幅広い世代に受け入れられ、現在では一般的な言葉になりました。
このように、使い勝手の良い言葉は、一時的な流行を超えて広く定着することが多いのです。
言葉の意味が直感的に伝わる
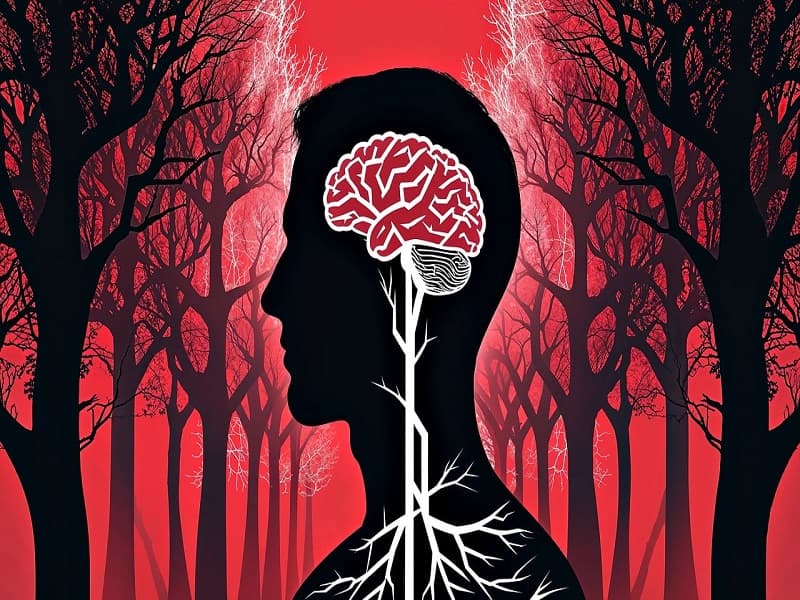
言葉の意味が分かりやすく、直感的に伝わるものは定着しやすいです。
例えば、「エモい」は、感動やノスタルジックな気持ちを表現する言葉として若者の間で流行しましたが、その意味がすぐに理解できるため、幅広い人々に受け入れられました。

分かりやすいからこそ、あっという間に広まるんだね!
反対に、「あげみざわ」などのように、意味を知らないと理解できない言葉は、流行が終わると使われなくなる傾向があります。
形を変えながら長く使われる

一部の若者言葉は、時代とともに形を変えながら生き残ることがあります。
例えば、「ウケる」という言葉は、もともと「ウケる(面白い)」として使われていましたが、
派生形として「ウケるんだけど」や「マジウケる」などの形が生まれ、長く使われ続けています。
このように、言葉自体は変化しても、基本的な意味が維持されることで、若者言葉が廃れずに生き残るケースもあります。
若者言葉の移り変わりを知るメリット
流行や時代の変化を理解できる

若者言葉の流行は、その時代の文化や価値観を反映しています。
例えば、「ぴえん」や「きゅんです」といった言葉は、SNSを中心に流行し、可愛らしい表現が好まれた時代の特徴を示しています。
言葉の変化を追うことで、どのような価値観が重視されているのか、時代のトレンドを理解する手がかりになります。
世代間のコミュニケーションが円滑になる
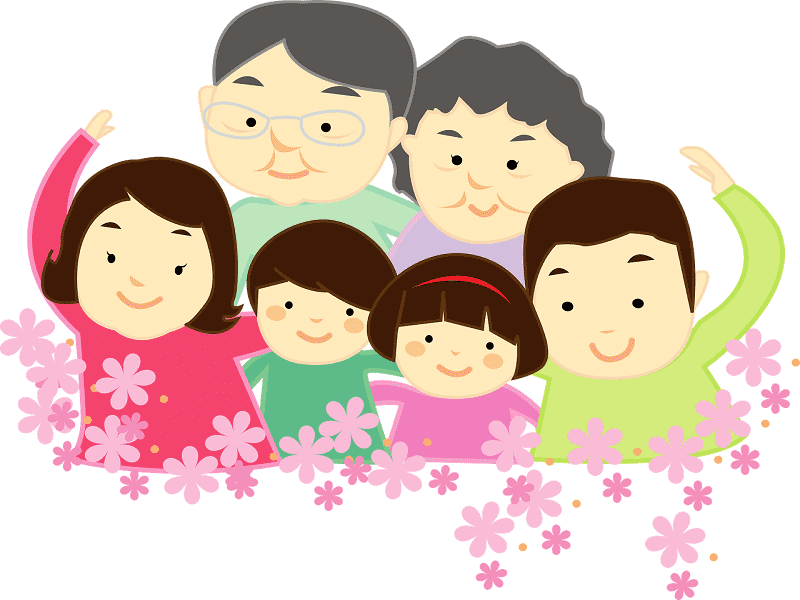
親世代や職場の上司などが若者言葉を理解していると、世代間のコミュニケーションがスムーズになります。
例えば、若者が「ガチでヤバい」と言ったときに、意味が分からなければ会話がかみ合わなくなることもあります。
若者言葉を知ることで、若い世代との会話が弾み、円滑なコミュニケーションにつながるでしょう。
マーケティングに活かせる

企業の広告や商品開発においても、若者言葉の理解は重要です。
流行の言葉を取り入れることで、ターゲット層に親しみを持ってもらいやすくなります。
例えば、「〇〇しか勝たん」という表現を広告に使うことで、若者に響くキャッチコピーを作ることができます。

「『〇〇しか勝たん』、これマストですね!」
ただし、流行が過ぎると一気に「古い」と感じられるため、適切なタイミングで使うことが重要です。
言葉の変化を楽しめる

若者言葉の移り変わりを知ることで、言葉の進化や変化を楽しむことができます。
たとえば、「マジ」という言葉が「マ?」に短縮されたり、「エモい」という言葉が広がったりする過程を追うことで、日本語のダイナミックな変化を実感できるでしょう。
言葉は常に変化し続けるものです。
若者言葉を知ることで、言葉の変遷を面白く感じることができるでしょう。
まとめ:死語一覧 2021と若者言葉の移り変わり

若者言葉は、その時代の流行や文化を反映し、短期間で広まりながらも、すぐに消えていくものが多いです。2021年に流行した言葉の多くも、すでに死語となっているものがあります。
しかし、一部の言葉は世代を超えて広まり、日常会話に定着するものもあります。
幅広い世代に使われる、日常会話で使いやすい、直感的に意味が伝わる言葉は、長く残る傾向があります。
若者言葉の変化を知ることで、時代のトレンドを理解したり、世代間のコミュニケーションを円滑にしたりすることができます。
言葉の移り変わりを楽しみながら、新しい表現を学び続けることが大切です。