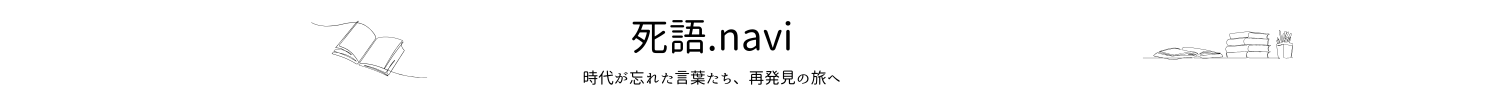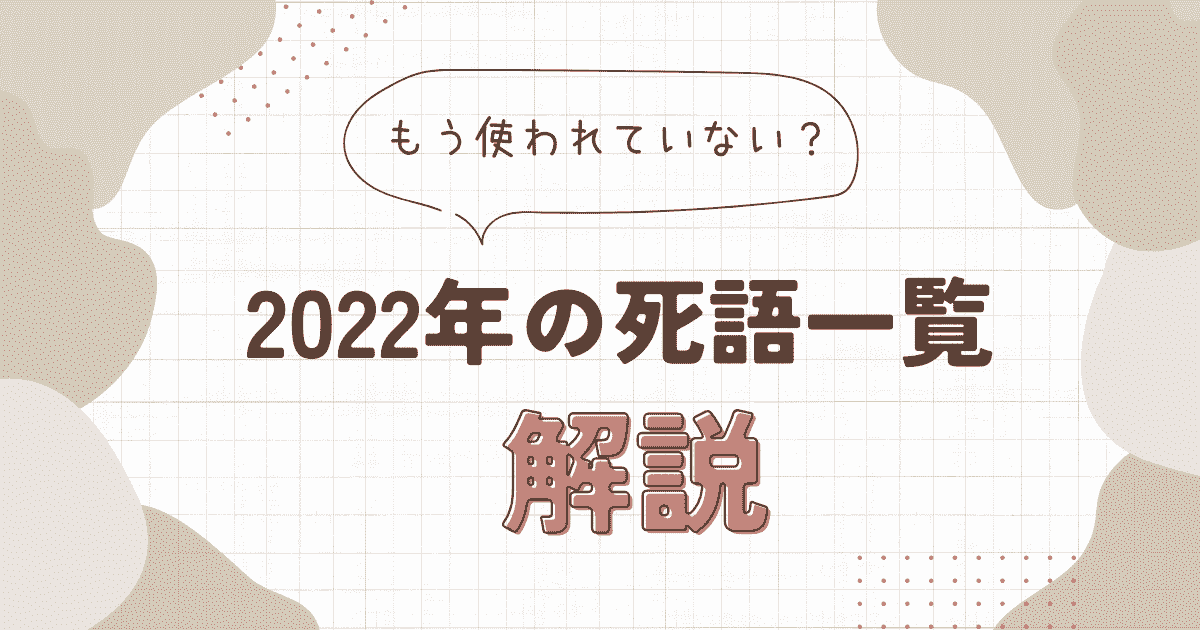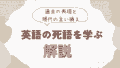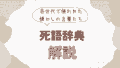時代とともに言葉の流行は移り変わり、かつてはよく使われていた言葉も次第に聞かれなくなります。
特に、若者言葉やネットスラングは変化が早く、一年経つだけで「もう古い」とされることも少なくありません。

あの頃の流行語、今じゃ死語かぁ…時の移ろい恐るべし
本記事では、2022年に流行したものの、今ではほとんど使われなくなった「死語」について詳しく解説します。
なぜ流行語が廃れるのか、具体的な言葉の例、そして死語を楽しむ方法についても紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
2022年の死語とは?使われなくなった言葉の特徴
流行の移り変わりが早い

近年の流行語は、SNSを中心に急速に広がる一方で、その寿命も短くなっています。
TikTokやTwitterなどで一気に広まった言葉は、短期間で飽きられ、次の流行語に取って代わられることが多いのです。

「流行語ってホント一瞬で消えるよね。」
例えば、2022年に流行した言葉も、2023年にはすでに「あれ?そんな言葉あったね」と言われることがあります。
これは、情報の消費スピードが速くなった現代ならではの現象と言えるでしょう。
若者言葉が一過性で終わる

若者の間で生まれる流行語は、一部の世代で爆発的に流行した後、自然と使われなくなる傾向があります。
特に中高生の間で使われる言葉は、その世代が成長すると共に廃れていきます。
また、特定の年齢層だけが使っていた言葉は、社会全体に定着することが少ないため、流行が終わると「死語」として扱われるようになります。
ネットスラングの寿命が短い

ネット上で生まれたスラングやミーム(ネットミーム)は、爆発的に広がるものの、
その分廃れるのも早いです。
特に、流行が動画コンテンツやSNS投稿によって広まる場合、一過性のブームで終わりがちです。

「流行語ってホント一瞬で消えるよね。」
例えば、ある言葉がバズっても、1〜2ヶ月後には新しいミームが登場し、
人々の関心はそちらへ移ってしまいます。
その結果、流行語があっという間に過去のものになってしまうのです。
メディアや芸能人の影響が大きい

テレビ番組やYouTube、TikTokのインフルエンサーが発信する言葉は、一時的に大流行することがあります。
しかし、発信者自身がその言葉を使わなくなると、一般の人々の間でも自然と使われなくなります。
特定の芸能人やコンテンツから広まった言葉は、流行のきっかけがなくなると急速に衰退する傾向があります。
そのため、こうした言葉は「死語」となるのも早いのです。
なぜ2022年の流行語が死語になるのか?
新しい流行語に置き換わるから

毎年、新しい言葉が生まれ、古い言葉は次第に使われなくなります。
特に、SNSのトレンドは移り変わりが激しく、常に新しい表現が求められるため、
古い言葉は自然と淘汰されます。

新しすぎる言葉、毎年発見が止まらない!
例えば、「ぴえん」が流行した後、「ぱおん」や「ぴえん超えてぱおん」といった派生語が生まれました。
しかし、これらも短期間で廃れ、次の流行語に置き換わっています。
SNSのトレンド変化が激しいから

Twitter、TikTok、InstagramなどのSNSでは、次々と新しいトレンドが生まれます。
そのため、一度流行した言葉でも、すぐに新しい言葉に取って代わられてしまいます。
特にTikTokでは、短い動画の中で流行語が多く生まれますが、流行が終わるのも早いのが特徴です。
2022年に流行した言葉の多くも、こうした短期間のトレンドの影響を受けていました。
使う世代が限られているから

若者言葉やネットスラングは、特定の世代でのみ使われるため、広く定着しにくいです。
そのため、若者が成長して言葉を使わなくなると、自然と死語になっていきます。
例えば、「それなー」や「きまZ」は中高生を中心に流行しましたが、社会人になるとあまり使われなくなり、結果として死語となりました。
流行を発信した人物・コンテンツの影響が薄れるから

特定のインフルエンサーやコンテンツが発信した言葉は、その影響力が薄れるとともに廃れていきます。
例えば、あるYouTuberが流行らせた言葉でも、
そのYouTuberの人気が落ちれば自然と使われなくなります。
こうした背景から、2022年に流行した言葉も、発信者やコンテンツの影響が薄れるとともに死語になったのです。
2022年の死語と元ネタ・流行の背景
きまZ(きまぜっと)
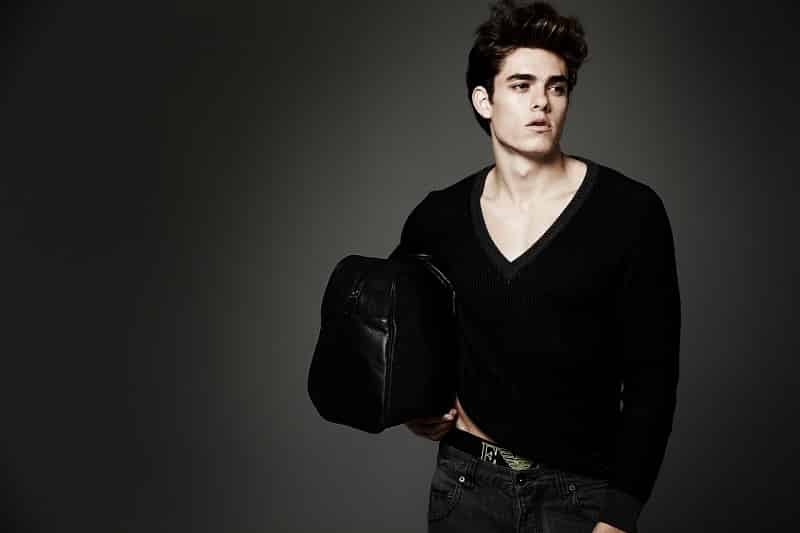
「きまZ」は、「決まっている(カッコいい)」を意味する若者言葉で、「Z」の語尾をつけることで独特の響きを持たせた表現です。
主に、TikTokやInstagramのストーリー投稿などで使われ、一部のインフルエンサーが使用したことで話題になりました。
特に、ファッションや髪型、ポーズなどが「完璧に決まっている」ことを表す際に用いられ、「今日のコーデ、きまZ!」といった使われ方をしていました。
また、「きまZ」ポーズと呼ばれる手の形を作るポーズも一時的に流行しました。
しかし、流行のピークが短く、2023年にはほとんど聞かれなくなっています。
理由としては、語感が一部の若者にしか受け入れられなかったことや、
新たな流行語に取って代わられたことが挙げられます。
それなー
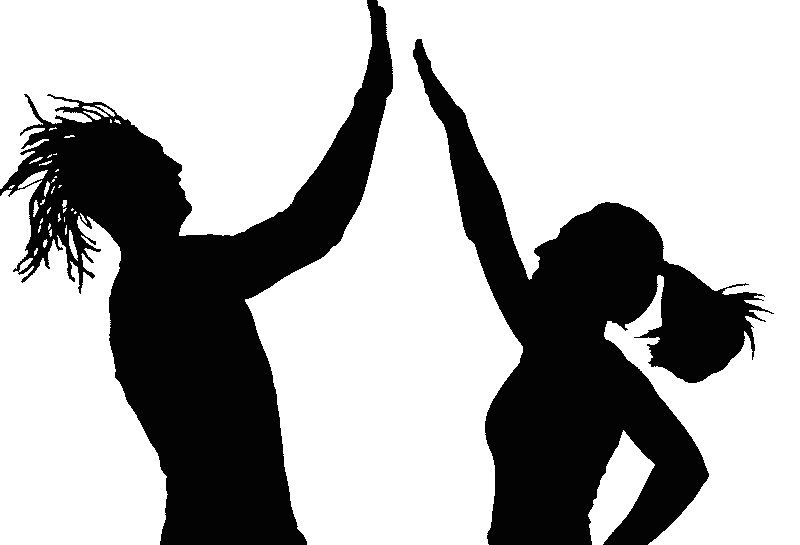
「それなー」は、誰かの発言に対して強く共感する際に使われた言葉で、「本当にそう思う」「マジで同感」といった意味を持ちます。
特に、中高生を中心にSNSやリアルの会話で頻繁に使われました。
この言葉は、2010年代後半から広まり、2022年の時点でも多くの若者に親しまれていました。
「それなー」と語尾を伸ばすことで、よりフレンドリーな雰囲気を演出できるのが特徴でした。
しかし、次第に「もう古い」「使っているとダサい」と認識されるようになり、
代わりに「ガチそれ」や「わかりみ」などの新しい表現が台頭したことで、次第に使われなくなっていきました。
現在では、一部の世代を除いてほとんど聞かれなくなっています。
「ぴえん」:泣き顔絵文字と共に流行

「ぴえん」は、悲しみや切なさを表現する言葉として若者の間で広まりました。
特に、泣き顔の絵文字(🥺)とセットで使われることが多く、SNSやLINEの会話で頻繁に登場しました。
さらに、「ぴえん超えてぱおん」などの派生語も登場し、一時は幅広い年代で使われるようになりました。
しかし、流行が短期間でピークを迎えたため、2023年頃にはすでに「古い」とされる言葉になっています。
「はにゃ?」:天然キャラの発言として人気
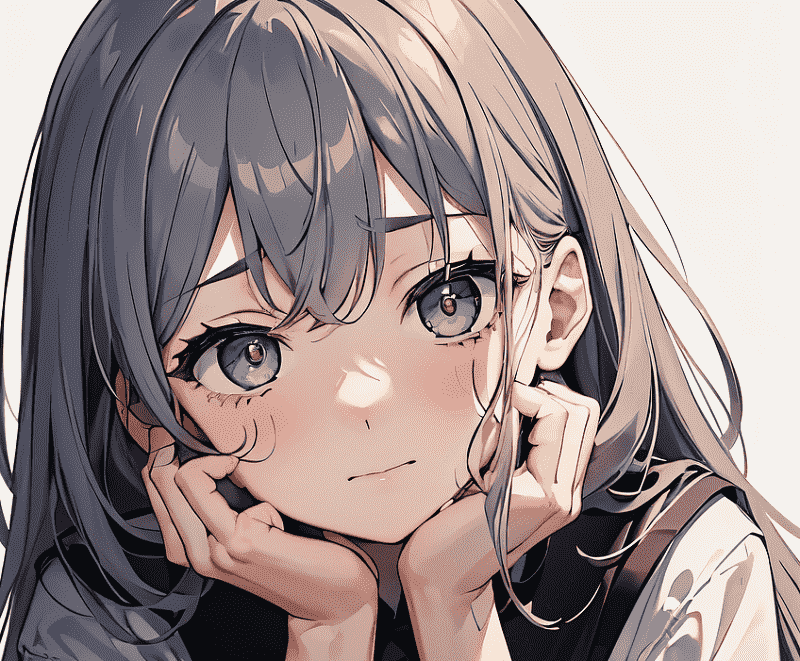
「はにゃ?」は、疑問や驚きを表現する言葉として2022年に流行しました。
この言葉は、天然キャラを演じる際によく使われ、可愛らしい印象を与えるのが特徴です。
主にTikTokの動画や配信者の間で使用され、多くの若者が日常会話で取り入れるようになりました。
しかし、流行が終わるとともに使用頻度が低下し、現在ではほとんど聞かれなくなっています。
「秒で」:即行動を表すネットスラング

「秒で」は、「すぐに」「一瞬で」という意味を持つネットスラングです。
特に、YouTuberやTikTokの動画内で「秒で○○する!」といった表現が多く使われたことで広まりました。
ただし、時間が経つにつれて新しい表現が登場し、「秒で」の使用頻度は低下しました。
現在では、特定の世代を除いてあまり使われなくなっています。
「バズる」:SNSの急激な拡散を意味

「バズる」は、SNSで投稿が爆発的に拡散されることを指す言葉です。
TwitterやTikTokで流行し、「このツイート、バズった!」といった形で使われていました。
しかし、近年では「バズる」という表現自体が古く感じられるようになり、新たな言葉に取って代わられつつあります。
現在では、「トレンド入りする」や「話題になる」といった言葉が使われることが増えています。
「大丈夫そ?」:親しみを込めた心配の表現
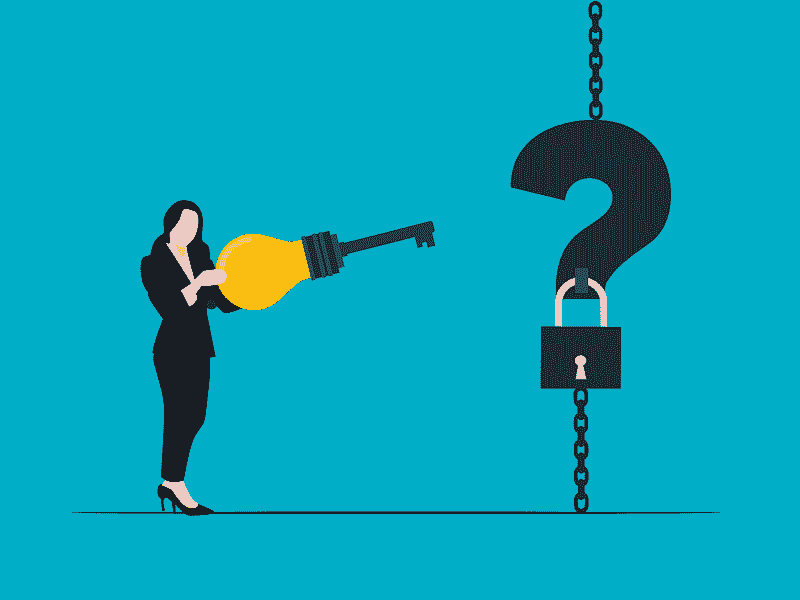
「大丈夫そ?」は、「大丈夫そう?」の省略形として2022年に若者の間で流行しました。
軽い心配やツッコミのニュアンスを込めた言葉として、SNSや日常会話で頻繁に使用されました。
しかし、次第に「軽すぎる」「適当な感じがする」といった理由で使われる機会が減り、2023年以降はほとんど聞かれなくなっています。
バブみ

「母親のような優しさや包容力を感じること」を指す言葉で、アニメ・ゲーム文化の中で流行しました。
2022年ごろまではオタク文化を中心に使われていましたが、
一般的な流行語としては定着せず、廃れてしまいました。
「母性を感じる」などの言い換え表現が普及したことも、死語化の要因の一つです。
やばたにえん
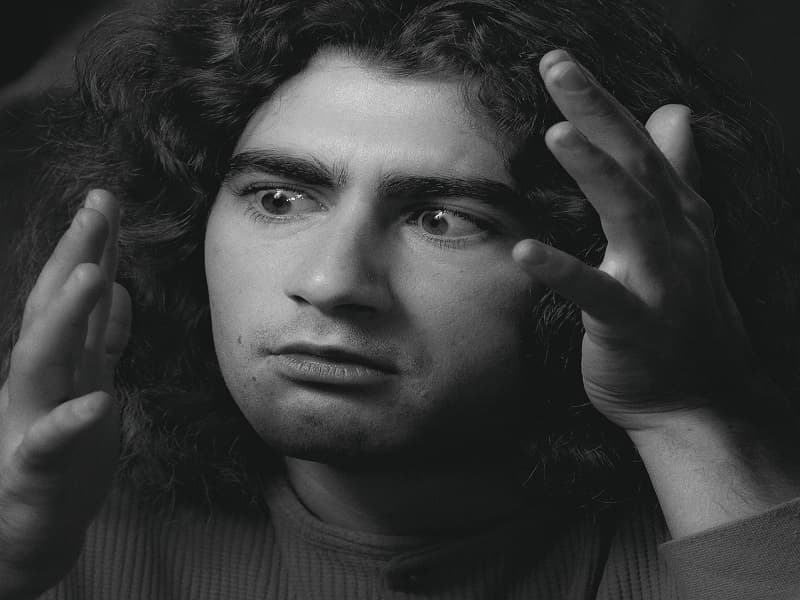
「やばい」と「たにえん(お茶漬けのメーカー)」を組み合わせた言葉で、
「とてもやばい」という意味で使われました。
2018年ごろからじわじわ流行し、2022年には若干のリバイバルを見せましたが、その後は急激に衰退しました。
「もう古い」と言われるようになり、現在ではほとんど使われません。
2022年の死語を今使うとどうなる?
古い人認定される
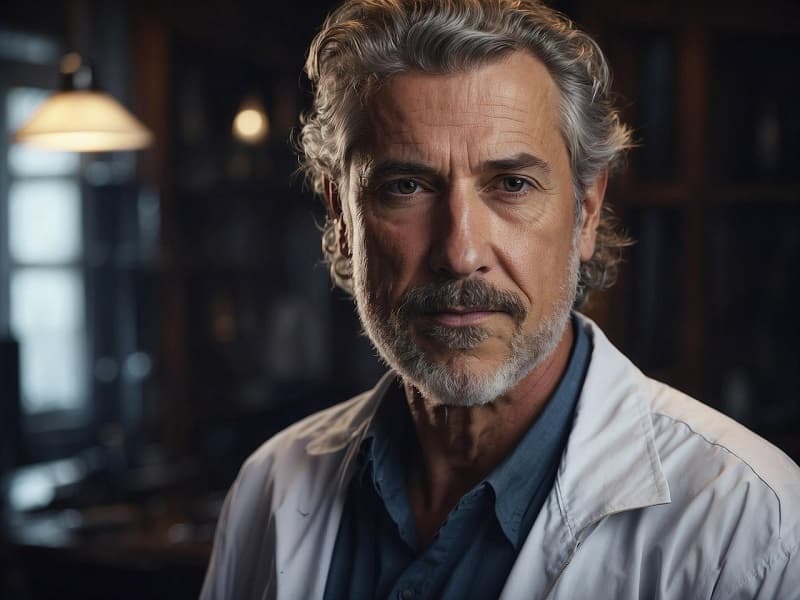
過去に流行した言葉を使うと、「もうその言葉、古いよ!」と言われてしまうことがあります。
特に、若者言葉の移り変わりが激しいため、流行が終わった言葉を使うと「世代を感じる」と思われることも。
例えば、「ぴえん」や「はにゃ?」を今使うと、「懐かしい」「おじさんっぽい」と思われる可能性が高いです。
一周回ってネタとしてウケることも

一方で、あえて昔の流行語を使うことで、ネタとして笑いを取れることもあります。
特に、若い世代同士の会話では、わざと古い言葉を使って盛り上がることがあります。
例えば、「それなー」と言うと、「懐かしい!」と話が弾むこともあるため、
場の雰囲気に合わせて使うのもアリかもしれません。
世代によって反応が違う

死語を使ったときの反応は、相手の年齢や世代によって異なります。
例えば、2022年当時に流行語を使っていた世代なら、懐かしさを感じるかもしれません。
しかし、若い世代や流行語に敏感な人ほど、「もうその言葉は古い」と感じやすいため、使用する際は注意が必要です。
死語の再ブームが起こる可能性もある

過去の流行語が再びブームになることもあります。
例えば、「エモい」や「ギャル語」のように、一度廃れた言葉が再評価されることも珍しくありません。
そのため、2022年の死語も数年後に「懐かしい」として再び流行する可能性があります。
懐かしの2022年の死語を楽しむ方法
あえて会話に取り入れてみる

友人や家族との会話の中で、あえて過去の流行語を使うと、懐かしさが盛り上がることがあります。
「それなー」「ぴえん」などを使って、当時の流行を振り返るのも楽しいでしょう。
当時のSNS投稿や流行を振り返る

TwitterやInstagramの過去の投稿を見返すと、「こんな言葉流行ってたな!」と懐かしく感じることがあります。
当時の流行した動画や投稿を振り返ることで、時代の移り変わりを実感できるでしょう。
死語クイズで遊ぶ
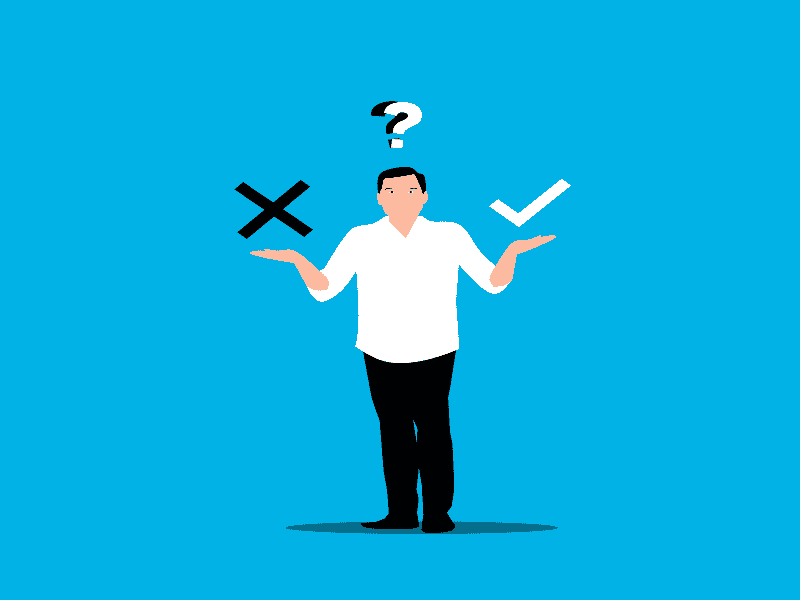
友達同士で「この言葉、覚えてる?」とクイズ形式で遊ぶのもおすすめです。
特に、世代の違う人と話すと、思いがけない発見があるかもしれません。
再流行の可能性を探る
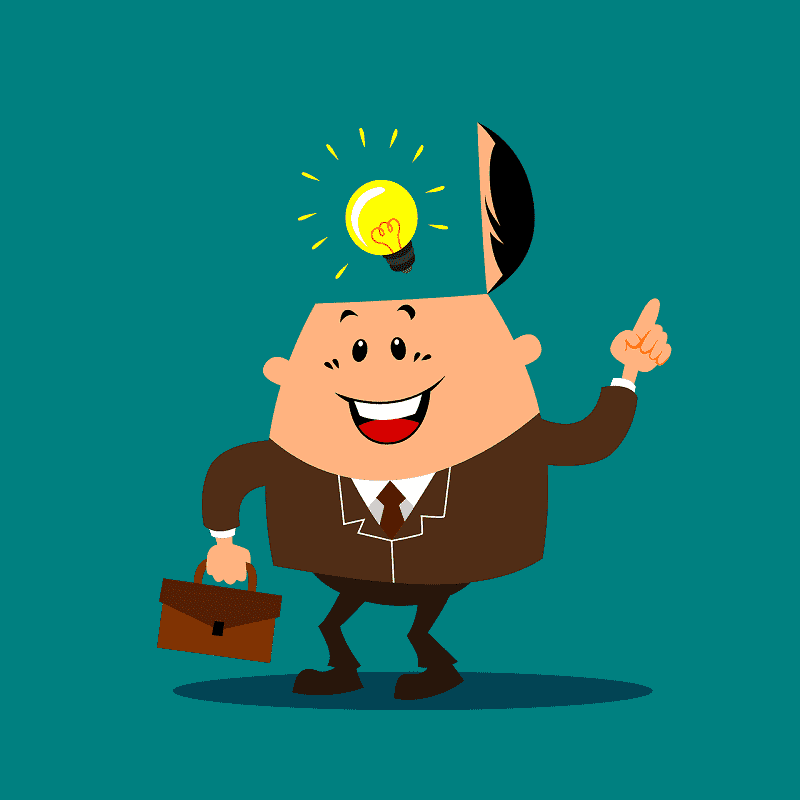
過去の流行語が再ブームになることもあるため、今後のトレンドを予想するのも面白いでしょう。
「この言葉、また流行るかも?」と考えることで、言葉の変化を楽しめます。
まとめ|もう使われていない?2022年の死語一覧

2022年に流行した言葉の多くは、現在ではあまり使われなくなり「死語」となっています。
しかし、それらの言葉には当時のトレンドや文化が反映されており、振り返ると懐かしさを感じることもあります。
言葉の流行は常に変化していますが、過去の言葉を知ることで、時代の移り変わりを楽しむことができるでしょう。