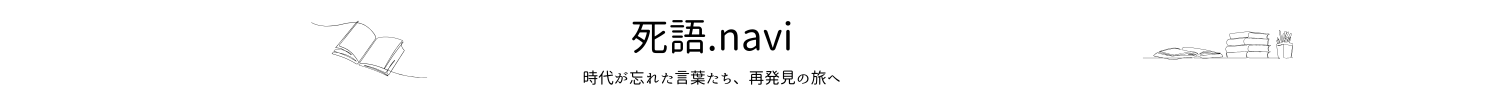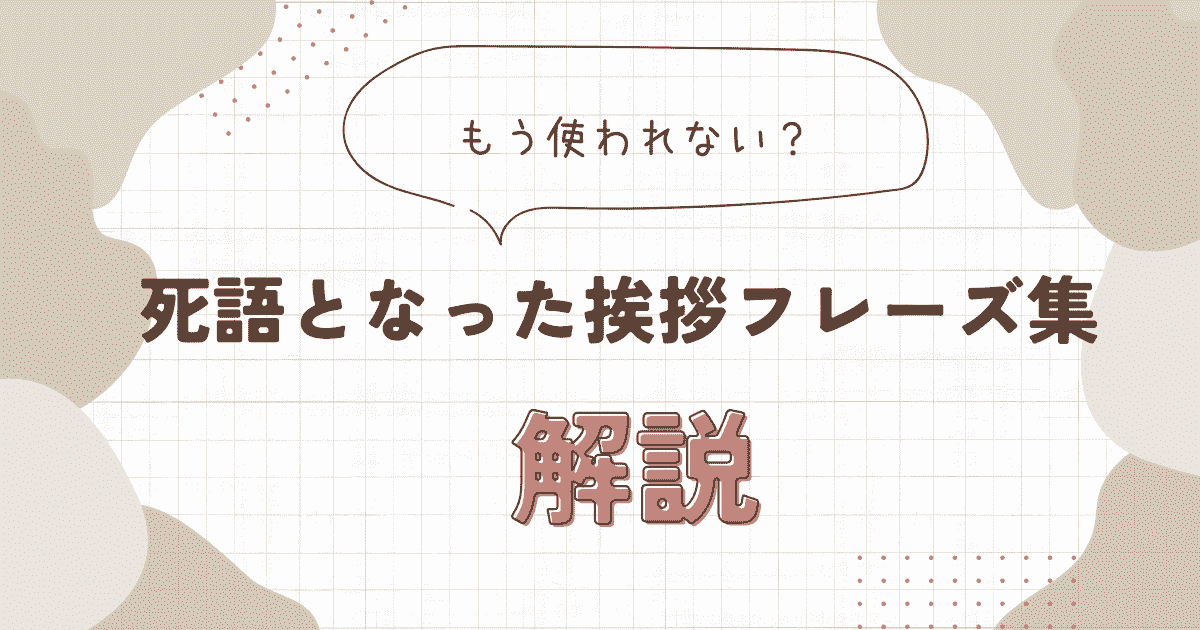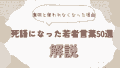昔はよく耳にしたのに、今ではあまり聞かなくなった挨拶のフレーズ。
時代とともに言葉は変わり、使われなくなった言い回しは「死語」と呼ばれます。
この記事では、かつて日常的に使われていた懐かしい挨拶の言葉や、その背景、
そして現代での受け取られ方について詳しく紹介します。

昔の挨拶、今なら思わず二度見しちゃう。
「なんだか懐かしい」「これ言ってたなぁ」と感じるような言葉がたくさん登場しますので、世代を超えて楽しめる内容です。
今では死語?昔よく使われた挨拶のフレーズとは
「ごきげんよう」は上品な別れの挨拶だったから

「ごきげんよう」は、かつて上品で礼儀正しい別れの挨拶として使われていました。
特に、女性の間で丁寧さを表すフレーズとして定着していました。
学校や家庭で日常的に使われることもあり、アニメや小説でもよく見られた言い回しです。
昭和〜平成初期の文化を感じさせる響きがあります。

ごきげんよう、言われるとちょっとドキッ
しかし現代では、堅苦しく古臭い印象を持たれることが多く、自然と使われなくなってしまいました。
今ではネタやジョークとして使われることがほとんどで、日常会話ではまず聞かれません。
「ハロー」は洋画や洋楽の影響で一時流行したから

英語の「Hello」がカタカナで「ハロー」として親しまれていた時期がありました。
特に1970〜80年代、洋楽や洋画の影響を強く受けていた日本では、オシャレで新しい響きとして流行しました。
テレビやラジオのDJが使ったり、アイドルの挨拶でも登場するなど、
ポップな雰囲気を醸し出していました。

ハローでイケてる時代の名残、今も好き!
しかし、今では英語に慣れた日本人が増えたことで、「ハロー」という言い回しは逆に古臭く感じられるように。
英語なら「ハイ」や「ヘイ」の方が一般的になり、「ハロー」はレトロな表現として扱われがちです。
「ちーっす」は若者の間で軽い挨拶として定着したから

「ちーっす」は、「こんにちは」や「お疲れさま」を軽く砕けた形で言い換えた若者言葉です。
1990年代〜2000年代前半にかけて、特に男子学生の間でよく使われていました。
ラフで気取らない雰囲気を出せるため、友達同士での挨拶にはピッタリでした。

当時の教室、男子たちは「ちーっす」で始まってた!
しかし、使われすぎた結果「ダサい」「古い」と思われるようになり、次第に若者の間でも敬遠されるように。
現代では、冗談っぽく使われることはあっても、日常的に使う人はかなり少なくなっています。
「ごめんあそばせ」はドラマやコントの定番セリフだったから

「ごめんあそばせ」は、主に昭和期の上流階級をイメージしたキャラクターが使うセリフとして知られています。
実際の会話ではほとんど使われていなかったものの、ドラマやコントで定番の言い回しでした。
このフレーズは、過剰な礼儀や丁寧さを演出するためのもので、いわば演出用の挨拶です。
そのため現代ではリアルな会話で使われることは皆無に近く、完全にネタ用の死語となっています。
「あら、ごめんあそばせ」などと使うと、昭和の雰囲気を感じさせるギャグのように受け取られます。
「あいよっ」は昭和の職人気質を感じさせる返事だったから

「あいよっ」は、「はいよ!」をさらに砕けさせた返答の言葉で、特に昭和の居酒屋や職人文化の中でよく使われていました。
料理屋の大将や市場の人が元気よく返事する際の定番で、威勢の良さや男気を感じさせる言い回しです。
しかし今の若者には馴染みが薄く、どこか芝居がかった印象を持たれることが多くなりました。

あいよっ、この威勢の良さ、今も伝えたい!
現代では懐かしい響きのある表現として扱われ、若い世代の間では完全に死語の仲間入りをしています。
死語になった挨拶が使われなくなった理由
時代の雰囲気や価値観が変わったから
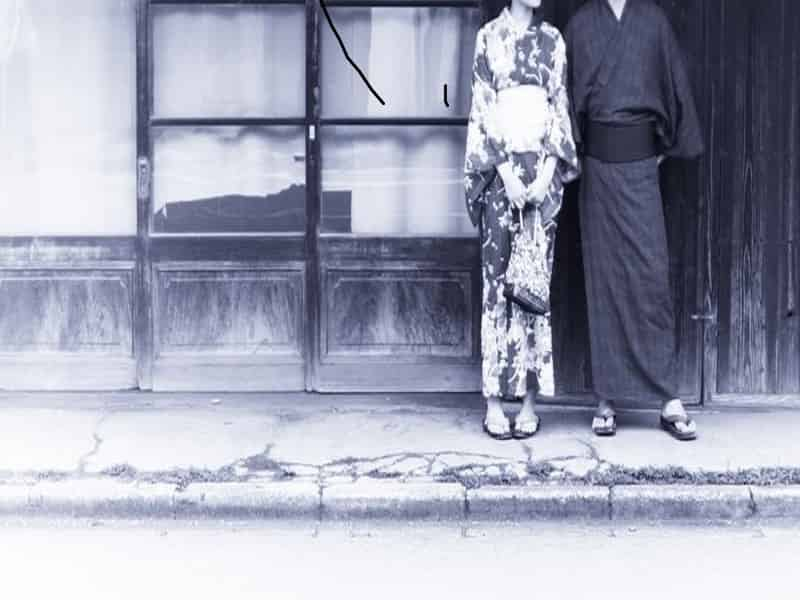
かつては丁寧さや格式を大切にしていた時代もありましたが、現代ではよりフランクでカジュアルなコミュニケーションが好まれるようになりました。
その結果、堅苦しい言葉や古風な表現は使いづらくなり、自然と日常の言葉から消えていくのです。
人々の価値観が「丁寧さ」から「気軽さ」にシフトしたことが、挨拶言葉の変化にも大きく影響しています。
言葉は文化を反映する鏡でもあり、時代を映す存在です。
ドラマやメディアの影響が薄れたから
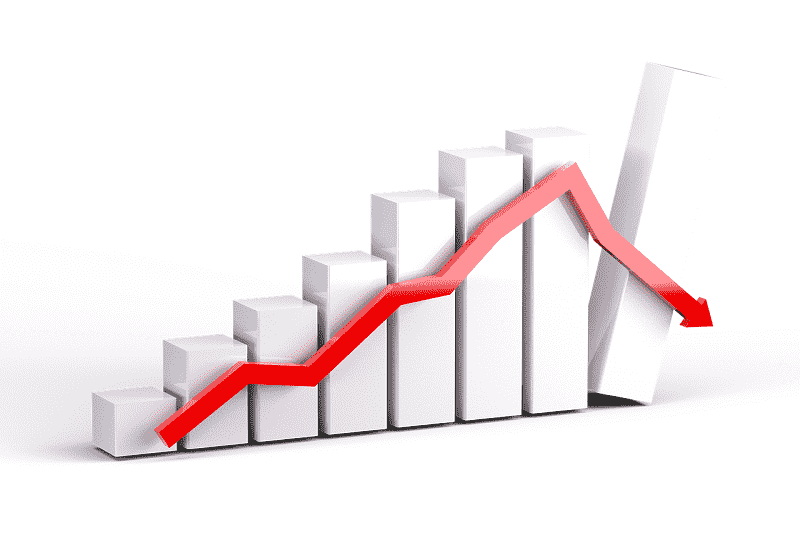
昭和や平成初期は、テレビ番組や映画、ラジオなどのメディアから多くの流行語が生まれていました。
挨拶の言葉も例外ではありません。
しかし、現代ではYouTubeやSNSなど、多様なメディアが存在しており、
一つの流行語が国民全体に広まることが少なくなりました。
これにより、特定の挨拶が流行して定着する機会も減ってきたのです。
メディアの多様化が、死語の誕生と密接に関わっているのです。
若者言葉やネットスラングが主流になったから

現在では、若者の間で使われる言葉やネットスラングが日常会話でも使われることが増えています。
挨拶一つとっても、昔のような丁寧語ではなく、短縮された軽い言葉が好まれる傾向にあります。
たとえば「おつ(お疲れ様)」「よろ(よろしく)」などは、もはや当たり前のように使われています。

敬語はどこへ?略語主流の時代かも
こうした新しい言葉の登場により、昔の言葉は使われなくなり、死語として忘れ去られていくのです。
言葉は世代とともに生まれ変わる存在なのです。
フォーマルさや礼儀の感覚が変化したから
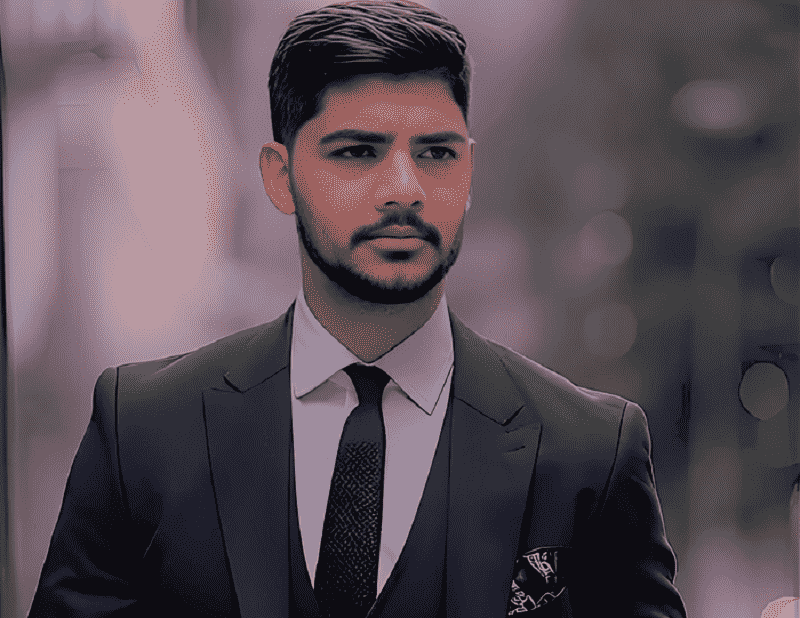
昔は、挨拶にもきちんとした形式やマナーが求められていました。
たとえば、上司に対しては「お疲れ様です」、目上の人には「ごきげんよう」など。
しかし現在は、職場でもフラットな人間関係が重視され、堅苦しい挨拶はかえって距離を感じさせるものとされることもあります。
社会全体の礼儀や距離感の変化が、言葉遣いの変化にも直結しているのです。
形式よりも「伝わる」ことが重視される時代なのです。
時代ごとの流行で見る死語となった挨拶の変化
昭和の時代はテレビ番組からの流行語が多かったから

昭和時代は、テレビが家庭に普及し、多くの人が同じ番組を見ていました。
そのため、テレビドラマやバラエティ番組から生まれた言葉が広く使われる傾向にありました。
「おはこんばんちは」などは、その典型例です。
これはアニメのキャラクターが使っていた挨拶で、
「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」を一つにまとめたユニークな言い回しです。

「おはこんばんちは」は最強の挨拶かも
また、コント番組でのお決まりのセリフがそのまま挨拶として流行したりと、
メディアの力が大きく作用していました。
昭和はメディア発信の挨拶が日常生活に自然と溶け込んでいた時代でした。
平成はギャル語や若者文化の影響が強かったから

平成になると、テレビに加えファッション雑誌やカリスマ読者モデルの影響が強くなりました。
若者文化が社会全体に影響を与え、特に「ギャル語」と呼ばれる言葉が急速に広まりました。
「やっほー」「ちーっす」などの挨拶は、そうした若者言葉の一部として定着しました。
また、プリクラ文化や携帯メールの普及により、短くてインパクトのある挨拶が好まれるように。
絵文字や顔文字も多用されました。
平成の挨拶は、若者の感性と新しいメディアの発展によって生まれた言葉が中心でした。
令和はSNSやスタンプで挨拶することが増えたから
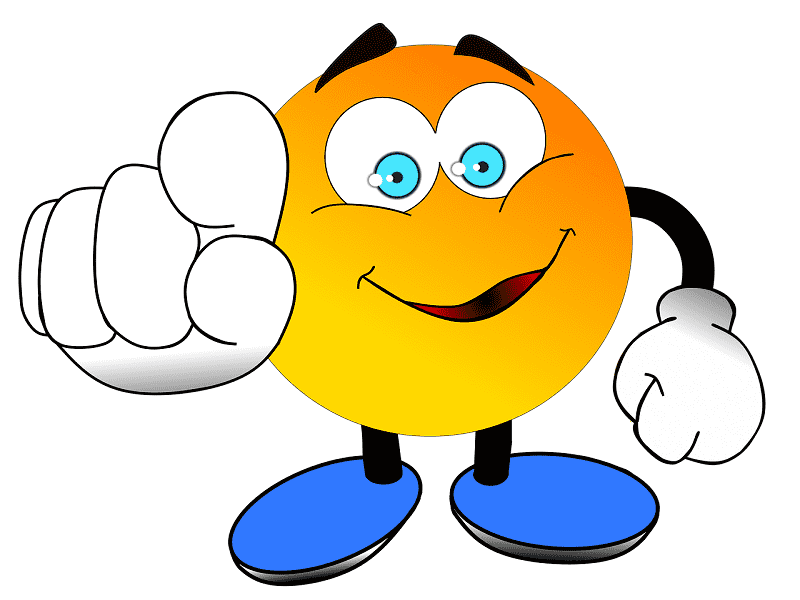
令和に入り、コミュニケーションの主な手段はSNSやチャットアプリへと移行しました。
LINEやInstagram、X(旧Twitter)などでは、テキストよりもスタンプや絵文字で感情や挨拶を伝えることが一般的になっています。
その結果、定型文のような挨拶フレーズは使われる機会が減り、表現の自由度が高くなりました。

令和の挨拶はスタンプと絵文字で決まり!
「おつ」「おはよーん」などの短縮系も多く使われましたが、これらも流行のサイクルが早いため、すぐに古い印象を持たれるようになります。
令和の挨拶は、言葉というよりも「感覚」で伝える時代に突入しています。
死語となった挨拶フレーズ集:懐かしい言い回し10選
ごきげんよう
丁寧で上品な別れの言葉。
今ではドラマや漫画の中でしか聞かれなくなりました。
使うと「お嬢様キャラ」のような印象を持たれることが多いです。
ちーっす
軽くてフレンドリーな挨拶。
かつては男子学生の定番でしたが、今では「古い」と思われがちです。
ハロー
一時期、洋楽や映画の影響で使われた挨拶ですが、現在ではあまり使われなくなりました。
おはこんばんちは
時間帯に関係なく使える便利な言葉としてアニメから流行しましたが、今では完全にネタ枠の言葉です。
どもども
軽く会釈するような挨拶。
「どーも」よりもさらに砕けた言い回しとして一時流行しました。
やっほー
主に女子の間で使われた元気な挨拶。
LINEやメールの冒頭でよく使われていました。
ごめんあそばせ
上流階級風の挨拶として、ドラマやコントでおなじみ。
今では完全にネタ用の死語です。
おっす
体育会系の男子や格闘技の世界でよく使われた挨拶。
今ではあまり耳にしません。
あいよっ
職人気質の人が返事として使っていた言葉。
勢いのある響きが特徴的でした。
まいどあり〜
関西弁で「いつもありがとう」という意味を込めた挨拶。
商人文化の名残ですが、最近では聞かれる機会が減っています。
死語となった挨拶を今使うとどう思われる?現代の反応とは
ネタとして面白がられることが多いから

死語の挨拶は、懐かしさや意外性から「ネタ」として使われることがよくあります。
特に、バラエティ番組やYouTube配信などで笑いを取る手段として使われることがあります。
わざと古い言葉を使うことで、ギャップやツッコミを誘う効果があるのです。
親しみを持たれることもあるから

世代が近い人同士であれば、「懐かしいね!」という共感が生まれることもあります。
特に同年代の友人との会話では、昔の挨拶が会話のきっかけになることも。
場違いに感じられてしまうこともあるから

しかし、TPOを間違えると「なんでその言葉?」と違和感を持たれる可能性もあります。
特に若い世代には意味が伝わらないことも。
世代間のギャップに注意が必要です。
死語とされる挨拶を使う場面と注意点
親しい人との会話なら使いやすいから

気心の知れた友人や家族との間では、死語もユーモアとして受け入れられやすいです。
懐かしい気持ちを共有できる相手なら、会話のアクセントとして効果的です。
ビジネスシーンでは避けた方がいいから

職場や取引先とのやり取りで死語を使うと、軽率に見られる可能性があります。
特にフォーマルな場では避けるのが無難です。
年代によって伝わらない可能性があるから

死語の多くは過去の流行に基づいているため、若い世代には意味が通じないことも。
ジェネレーションギャップを感じさせないよう注意が必要です。
SNSや配信ではウケを狙って使えることもあるから

ネットでは「懐かしの言葉シリーズ」などの企画で、あえて死語を使うのもアリです。
視聴者の反応を見ながらうまく使えば、面白い演出として活用できます。
SNSや若者言葉にもある?新たな死語挨拶の兆し
「おつ」「おはよーん」などはすでに古いとされているから

「おつ」は「お疲れ様です」の略語で、今でもよく見かけますが、すでに「古く感じる」という声も出ています。
「おはよーん」も、テンションが高めの挨拶として一時期流行しましたが、現在ではあまり使われていません。
「ぴえん」「よき」なども使う人が減ってきているから
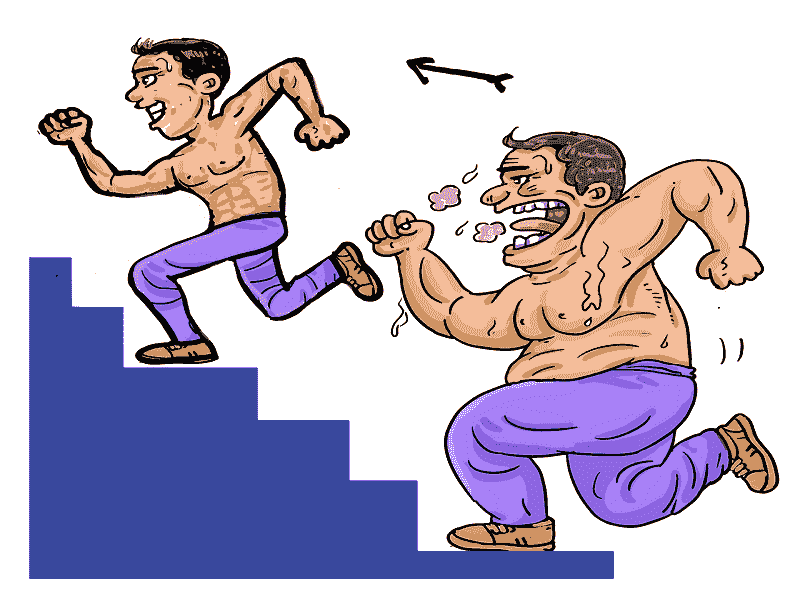
2020年前後に流行した「ぴえん」や「よき」なども、若者言葉として短期間で爆発的に広まりましたが、今では「もう古い」と感じる人が増えています。
スタンプや絵文字に挨拶が置き換わっているから

LINEなどでは、言葉を打たずにスタンプ1つで挨拶や感情を伝えることが一般的になっています。
文字の挨拶自体が省略される時代になってきているのです。
流行のサイクルが早くなっているから

SNSの普及により、言葉の流行はこれまで以上に速くなっています。
新しい挨拶言葉が生まれては、数か月で廃れるということも珍しくありません。
今使っている挨拶も、数年後には「懐かしい」「死語」になる可能性があるのです。
まとめ|死語と挨拶の関係を知って言葉を楽しく使おう

挨拶の言葉も時代とともに変化し、使われなくなるものがたくさんあります。
けれども、死語と呼ばれる言葉には、その時代を象徴する面白さや背景があります。
昔の挨拶を知ることで、言葉の歴史や文化の移り変わりが見えてきます。
普段の会話で使う機会は少なくなっても、懐かしい気持ちで楽しんだり、ネタとして使ったりするのも一つの方法です。
言葉を通して時代を旅するような感覚で、死語となった挨拶を楽しんでみてはいかがでしょうか?