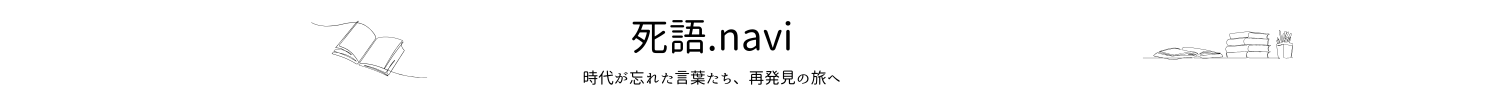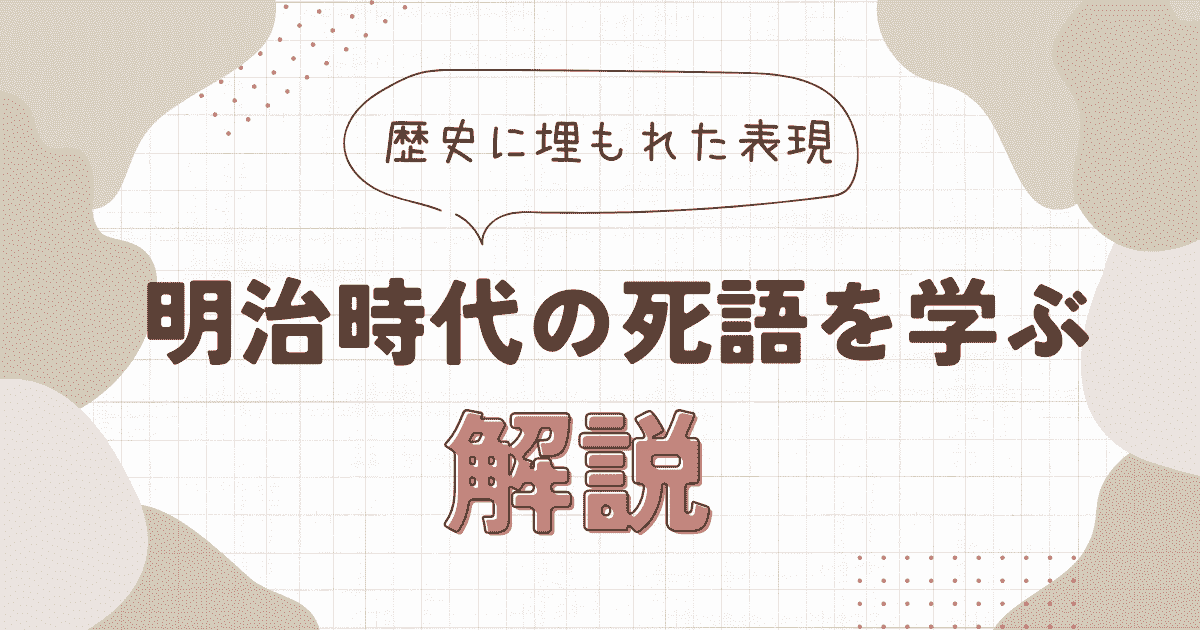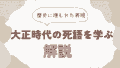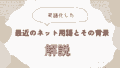明治時代は、日本が近代化へと大きく舵を切った時代でした。
文明開化や西洋文化の流入によって、新しい言葉が次々と生まれ、それまで使われていた言葉の多くが廃れていきました。
明治時代の言葉を学ぶことで、当時の価値観や社会の変化を知ることができます。

明治レトロ、意外と新鮮かも!
本記事では、明治の死語とその背景について詳しく解説し、当時の文化や風習にも触れていきます。
明治の死語とは?時代とともに消えた言葉

明治時代の死語とは、明治時代に広く使われていたものの、現代ではほとんど耳にすることがなくなった言葉を指します。
西洋からの新しい概念や技術の導入により、多くの言葉が変化し、古い表現は徐々に廃れていきました。
また、当時の生活習慣や文化に根付いた言葉も、時代の流れとともに消えていったのです。
なぜ明治時代の言葉は死語になったのか?
西洋文化の影響で新しい言葉が生まれたから

明治時代は、日本が近代化を目指し、西洋の文化や技術を積極的に取り入れた時代でした。
その結果、英語やフランス語由来の言葉が増え、従来の日本語表現が使われなくなりました。
例えば、従来の「御目見得(おめみえ)」は「面会」という言葉に置き換えられました。
言葉の統一が進み、方言や古い表現が淘汰されたから

明治政府は、国民の意識統一を図るために標準語を推奨しました。
これにより、地方ごとに異なっていた表現や、武士が使っていた言葉が徐々に消えていきました。
例えば、江戸時代には「いとおかし(とても趣がある)」という表現がありましたが、現代ではほとんど聞かれなくなっています。
生活様式や価値観の変化によって使われなくなったから

明治時代には、人々の生活様式が大きく変化しました。
西洋式の教育や産業革命の影響で、従来の日本的な言葉が不要になっていきました。
例えば、「やんぬるかな(もはやどうしようもない)」という表現は、古典的であり、現代ではほとんど使われません。
戦後の国語改革で廃れた表現があるから

第二次世界大戦後、日本語の簡略化が進められ、旧仮名遣いや漢語表現が見直されました。
これにより、明治時代に使われていた難解な表現が徐々に姿を消しました。
例えば、「ちょぼちょぼ(少しずつ)」といった言葉も、時代とともに使われなくなりました。
明治の死語・代表的な表現一覧
「いとおかし」(とても趣がある)

平安時代から使われていた表現で、明治時代にも文学作品などで使われていました。
現在では古典文学の中でしか見られません。
「てんでに」(各自で、思い思いに)

明治時代の日常会話で使われていましたが、現代では「それぞれ」や「バラバラに」といった言葉に置き換えられました。
「やんぬるかな」(もはやどうしようもない)
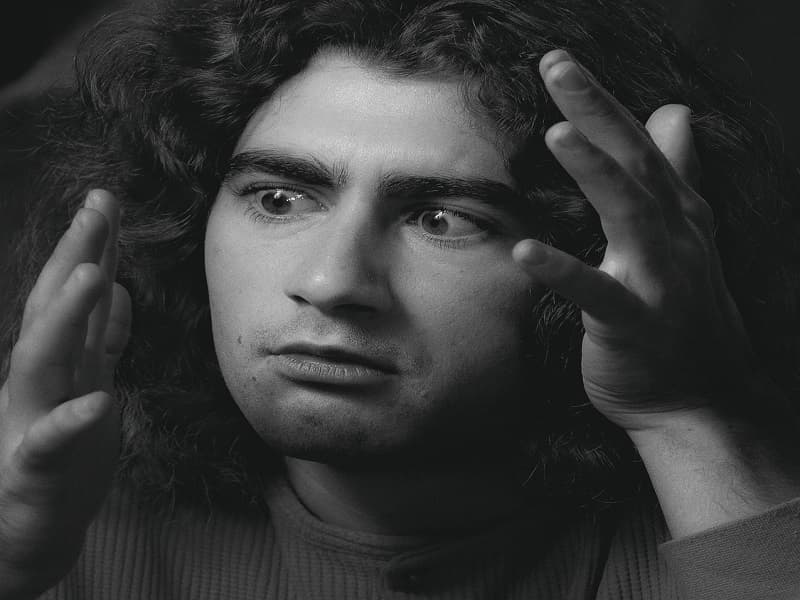
「これはもうどうにもならない」という意味で使われた古風な表現です。
現代では「もうダメだ」や「手遅れだ」といった表現が一般的です。
「ちょぼちょぼ」(少しずつ)

「少しずつ、ぽつぽつと」という意味で使われていました。
現在では「ぼちぼち」といった似た表現が使われることがあります。
「ごきげんよう」(挨拶の言葉)

上品な挨拶の言葉として使われていましたが、現在ではほとんど耳にしません。
ただし、一部の学校では今でも伝統的な挨拶として残っています。
現代に残る明治時代の言葉とその変化
「御用」(昔は役所の仕事、現在は警察関連の言葉)

明治時代には「お役所仕事」という意味で使われていましたが、現在では「御用だ!」のように、警察関連の言葉として残っています。
「先生」(昔は武士や師匠を指し、現在は教師や医師の呼称)

かつては文人や学者、武士の師匠を指す言葉でしたが、現代では教師や医師を指す言葉として定着しました。
「旦那」(昔は裕福な家の主人、現在も使われるが意味が変化)

明治時代には裕福な商人や家の主人を指していましたが、現代では夫を指す言葉として使われるようになりました。
「演説」(明治の政治用語、現在も使われるがニュアンスが変わった)

明治時代に政治家が民衆の前で話すことを指していましたが、現在では広く「スピーチ」の意味で使われています。
まとめ:明治の死語を学び、日本語の歴史を知る

明治時代の死語を学ぶことで、当時の日本社会の変化や価値観の移り変わりを知ることができます。
西洋文化の流入や近代化の影響で、多くの日本語表現が淘汰されていきましたが、その一方で、現代にも残る言葉も少なくありません。
明治の言葉を振り返ることで、日本語の奥深さを再発見し、歴史をより身近に感じることができるでしょう。