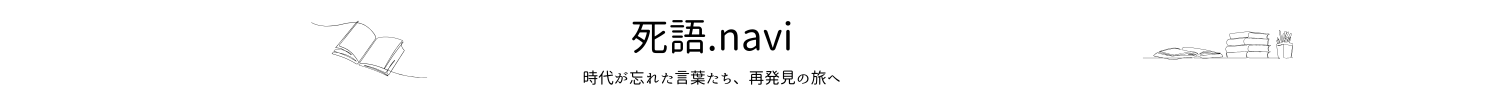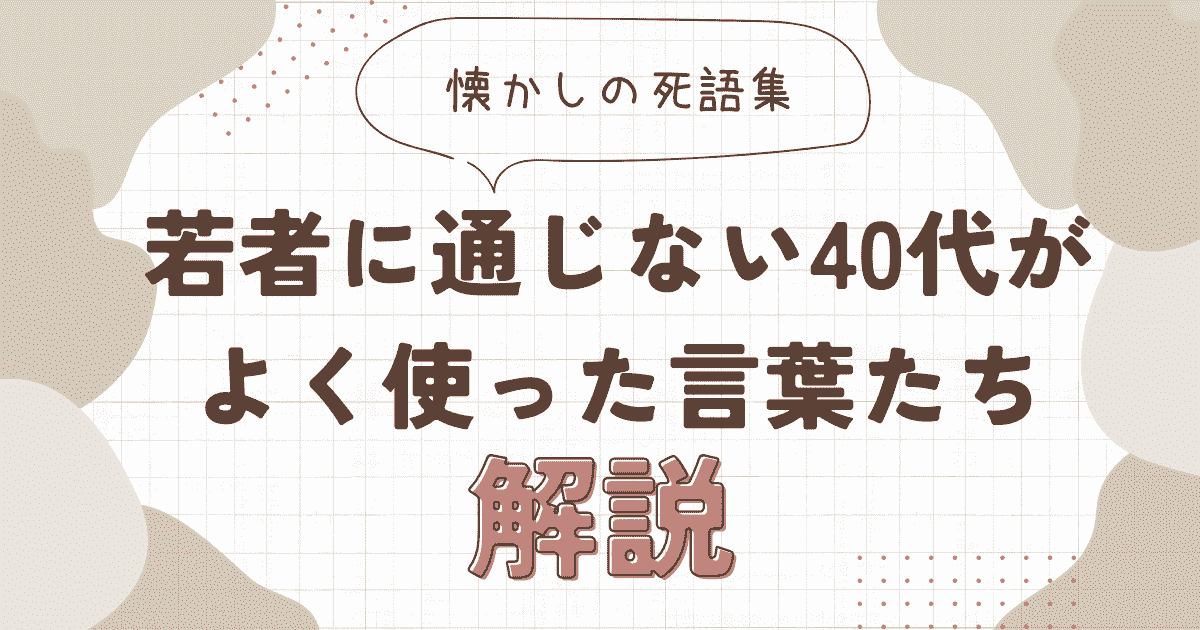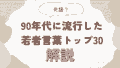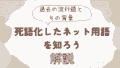時代の流れとともに、流行した言葉も徐々に使われなくなり、やがて「死語」となってしまいます。
特に40代が若い頃によく使っていた言葉の多くは、現在の若者には通じなくなってきました。

死語だったワード、令和に復活あるかも?
本記事では、そんな懐かしい死語を紹介しながら、なぜ言葉が廃れてしまうのかを探ります。
また、一部の言葉は形を変えて復活することもあります。
果たして、かつての流行語たちは再び日の目を見ることがあるのでしょうか?
40代がよく使った言葉が「死語」になった理由とは?
時代の変化とともに言葉も変わるから

時代が進むにつれて、人々のライフスタイルや価値観も変化します。
それに伴い、言葉の使われ方も変わるため、過去に流行した言葉が廃れるのは自然なことです。

わかる〜言葉も時代とともに変わっちゃうよね!
例えば、昔は電話が主なコミュニケーション手段でしたが、今ではLINEやSNSが主流となり、会話のスタイルも大きく変わりました。
その結果、当時の流行語が使われなくなってしまうのです。
インターネットやSNSの普及で新しい言葉が生まれたから

現代では、インターネットやSNSを通じて新しい言葉が次々と生まれています。
Twitter(X)やTikTokなどのプラットフォームでは、短期間で流行語が生まれ、消えていくことが一般的です。

流行語、秒で消えるのマジ驚くわー
かつての流行語は、テレビや雑誌を通じて広まることが多かったですが、現在はSNSが中心となり、言葉の入れ替わりがさらに加速しています。
テレビや雑誌の影響力が弱まったから

昔は、テレビ番組や雑誌が流行の発信源でした。
タレントや芸能人が使った言葉がそのまま流行語となり、全国的に広まることがありました。
しかし、現在はテレビ離れが進み、個人が情報を発信できる時代になっています。

SNSでの発信力、まさに今が主役かも!
そのため、特定の言葉が長期間にわたって定着することが難しくなりました。
若者の流行が短期間で移り変わるから

若者文化の特徴のひとつに、「飽きやすさ」があります。
一度流行った言葉も、数ヶ月もすれば「もう古い」と見なされ、次の新しい言葉に取って代わられます。

若さって、常に新しいのを追いかけるよね
特に、SNSの影響で流行のサイクルが短くなったため、40代が若い頃に使っていた言葉は、今の若者にはほとんど知られていないのが現状です。
懐かしの死語集:40代がよく使ったが若者に通じない言葉一覧
「チョベリバ」「チョベリグ」

「チョベリバ」は「超ベリー・バッド(Very Bad)」の略、
「チョベリグ」は「超ベリー・グッド(Very Good)」の略です。
1990年代に女子高生を中心に流行しました。
「アッシー」「メッシー」「ミツグ君」

バブル時代に流行した言葉で、
「アッシー」は車で送り迎えをしてくれる男性、
「メッシー」は食事を奢ってくれる男性、
「ミツグ君」は女性に貢ぐ男性を指します。
バブル崩壊後、こうした言葉はほとんど聞かれなくなりました。
「バイビー」「バッチグー」

「バイビー」は「バイバイ」と「ベイビー」を合わせた別れの挨拶で、
「バッチグー」は「バッチリ」と「グッド(Good)」を組み合わせた表現です。
どちらも1980年代から1990年代にかけて使われましたが、現在ではほぼ死語になっています。
「ナウい」「イケイケ」
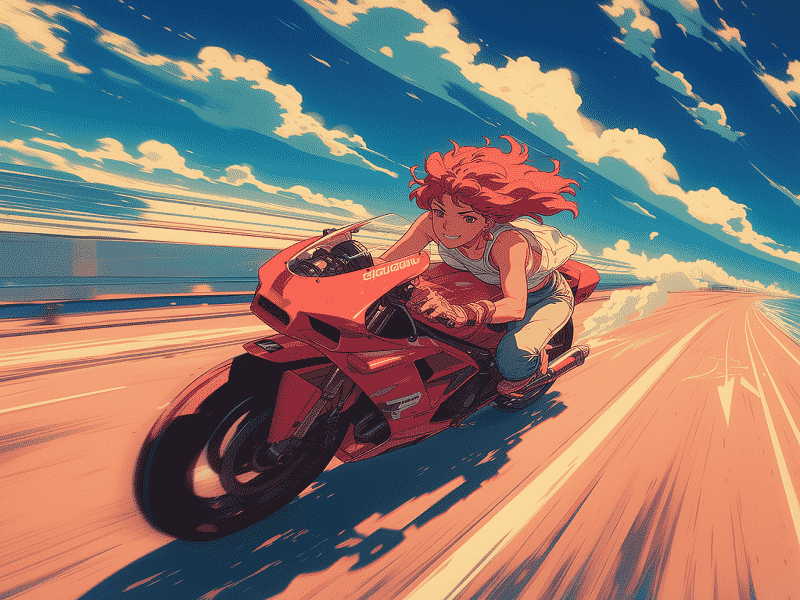
「ナウい」は「今風」という意味の言葉で、
「イケイケ」は勢いのある様子を表します。
どちらもバブル期の流行語ですが、現在ではほとんど使われていません。
「ズッコケる」「アウトオブ眼中」

「ズッコケる」は転ぶようなリアクションをすること、
「アウトオブ眼中」は「まったく興味がない」という意味で使われていました。
現在の若者には馴染みがなく、通じにくい言葉のひとつです。
「オヒョイ」「ガビーン」

「オヒョイ」は驚いたときの表現で、
「ガビーン」はショックを受けたときのリアクションです。
どちらも1970年代から1990年代にかけてよく使われましたが、現在では完全に死語となっています。
バブル時代の死語:40代には懐かしいけど若者には通じない言葉
「ワンレン・ボディコン」

「ワンレン」はワンレングスの略で、前髪なしで長さを均一に揃えたストレートヘアのことを指します。
「ボディコン」はボディ・コンシャス(Body Conscious)の略で、体のラインを強調するピッタリとしたドレスやファッションのことです。
バブル時代の女性たちにとって、このスタイルは一種のステータスでしたが、現在ではほぼ死語となっています。
「ジュリアナ東京」「お立ち台」

「ジュリアナ東京」は、1990年代初頭に大人気だったディスコの名前です。
「お立ち台」は、そのジュリアナ東京などのクラブで女性がダンスをするための高いステージのことを指します。
この文化はバブル時代を象徴するものの一つでしたが、今の若者にはまったく馴染みがありません。
「3高(高身長・高学歴・高収入)」
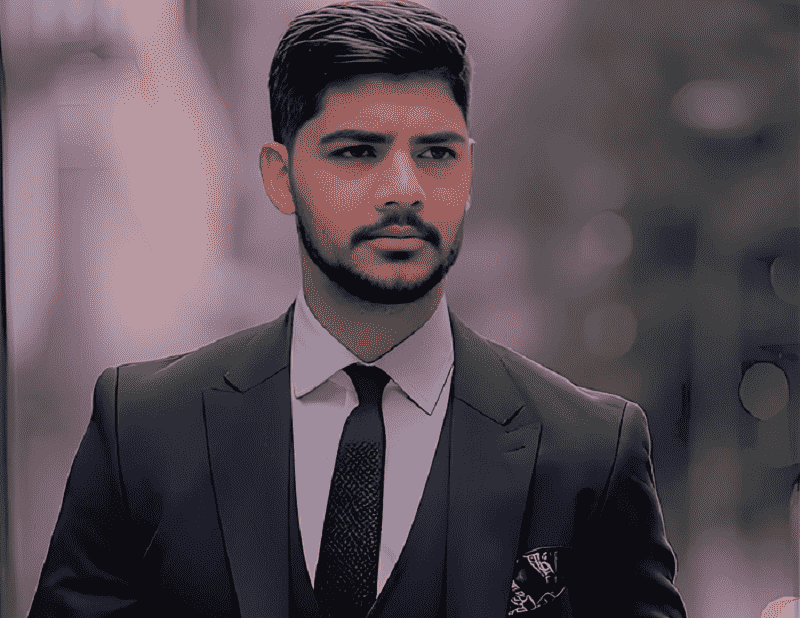
バブル時代、女性の理想の男性像として「3高」という言葉がありました。
これは「高身長・高学歴・高収入」の三拍子が揃った男性のことを意味します。
現在では、結婚観や価値観が多様化し、「3高」にこだわる人は減っています。そのため、この言葉もほぼ死語となりました。
「24時間戦えますか?」

これは、1989年に放送された栄養ドリンク「リゲイン」のCMのキャッチフレーズです。
バブル期の猛烈な働き方を象徴する言葉として流行しました。
現在では、働き方改革が進み、長時間労働が問題視される時代になったため、ほぼ使われることはありません。
「成田離婚」

新婚旅行から帰ってきた直後、成田空港で別れてしまうことを指す言葉です。
バブル期には、派手な結婚や海外旅行が流行し、価値観の違いからこのようなケースが増えました。
現在では、結婚のあり方が変わり、「成田離婚」という言葉自体を耳にすることはほとんどなくなっています。
「アーバン」「ソバージュ」

「アーバン」は「都会的で洗練された」という意味で使われていた言葉です。
「ソバージュ」は、1980年代に流行したパーマスタイルで、細かいウェーブをつける髪型を指します。
どちらの言葉もバブル期にはよく使われましたが、今では死語となっています。
平成初期の死語:40代がよく使ったが今では聞かない言葉
「ガラケー」「ポケベル打ち」

「ガラケー」は「ガラパゴス携帯」の略で、日本独自の進化を遂げたフィーチャーフォンを指します。
スマートフォンが普及する前は主流でしたが、現在ではほとんど見かけなくなり、「ガラケー」という言葉自体も使われなくなりました。
「ポケベル打ち」は、ポケットベルでメッセージを送る際に、数字キーを使って文字を入力する方法のことです。
1990年代には、数字の組み合わせで文字を打つ「ポケベル語」が女子高生の間で流行しましたが、ポケベル自体が廃れたため、この言葉も完全に死語となっています。
「カセットテープ」「MD(ミニディスク)」

「カセットテープ」は、音楽を録音・再生するための磁気テープを使ったメディアです。
1970年代から1990年代にかけて広く使われましたが、CDやデジタル音楽の普及により、現在ではほとんど使われていません。
「MD(ミニディスク)」は、ソニーが開発したデジタル音楽メディアで、1990年代後半から2000年代初頭にかけて流行しました。
しかし、MP3プレイヤーやスマートフォンの登場により、こちらも姿を消し、「MD」という言葉自体も若者には馴染みがなくなっています。
「プリクラ帳」「ルーズソックス」

「プリクラ帳」は、プリクラ(プリント倶楽部)で撮った写真を貼り付けるためのノートのことです。
平成初期の女子高生の間では、友達同士でプリクラを交換し、プリクラ帳を作るのが定番でした。
「ルーズソックス」は、1990年代に女子高生の間で流行した、足元がダボッとした長い靴下です。
かつては制服に合わせるのが主流でしたが、2000年代以降はすっかり見かけなくなりました。
ただし、最近は一部の若者の間で「平成レトロ」として再び注目されることもあります。
「アムラー」「シノラー」
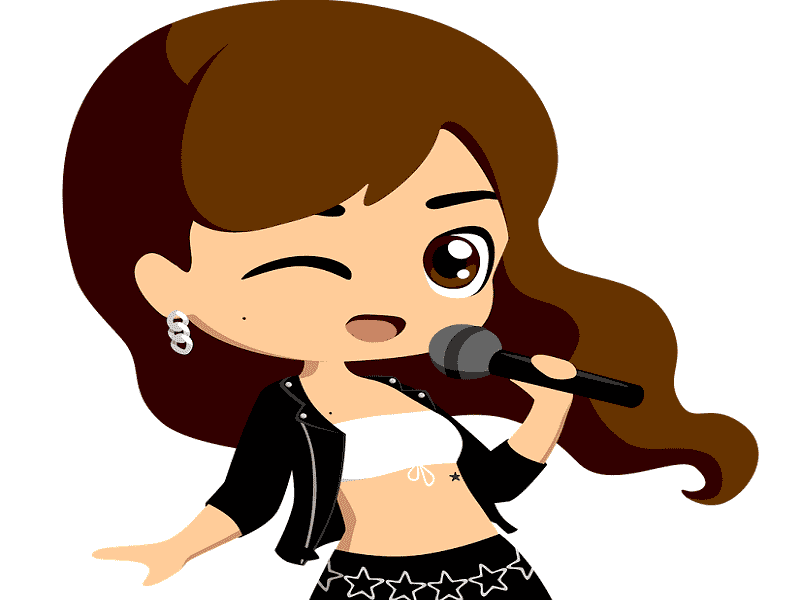
「アムラー」は、歌手・安室奈美恵さんのファッションや髪型を真似する若者たちを指す言葉です。
1990年代後半に大流行し、ミニスカートや厚底ブーツ、細眉などのスタイルが「アムラー」として認知されました。
「シノラー」は、タレントの篠原ともえさんの個性的なファッションを真似するスタイルのことを指します。
カラフルな衣装や髪型、独特のハイテンションなキャラクターが特徴でした。
どちらの言葉も当時の流行を象徴していましたが、現在ではあまり使われることがなくなっています。
「KY(空気読めない)」

「KY」は、「空気読めない」の略で、周囲の雰囲気を察することができない人を指す言葉です。
2000年代前半に流行し、若者の間で頻繁に使われました。
しかし、現在では「エモい」「ガチ勢」「陰キャ・陽キャ」などの新しいスラングが登場し、「KY」はほとんど聞かれなくなりました。
また、「空気を読む」という考え方自体が薄れつつあるため、この言葉の存在感も低下しています。
「ドロンします」「ズンドコベロンチョ」

「ドロンします」は、「こっそり姿を消す」という意味で使われていた言葉です。
時代劇などで忍者が煙玉を使って消えるシーンをイメージした表現で、昭和から平成初期にかけて使われていました。
「ズンドコベロンチョ」は、1991年に放送された『世にも奇妙な物語』のエピソードのタイトルです。
作中では意味不明の言葉として登場し、視聴者の間で
「意味はわからないけれど、なんとなく面白い言葉」として広まりました。
しかし、どちらも若者の間ではほとんど使われなくなり、完全に死語となっています。
40代の会話で今も登場する?死語になりかけの言葉
「微妙」「激ヤバ」

「微妙」は、「あまり良くない」「なんとも言えない」といった意味で使われる表現です。
1990年代から2000年代にかけてよく使われましたが、若者の間ではあまり聞かれなくなってきています。
「激ヤバ」は、「非常にヤバい」という意味で、1990年代後半に流行しました。
「ヤバい」自体は今の若者も使いますが、「激ヤバ」という表現はあまり耳にしなくなりました。
「マジで?」「てか」

「マジで?」は、驚いたときや疑問を持ったときに使う相槌の一つです。
これは今でも広く使われていますが、若者の間では「ガチ?」や「えぐくね?」といった表現が主流になりつつあります。
「てか」は、話を切り替えるときに使う言葉ですが、最近の若者の間では「ていうか」「てかさ」のような形で使われることが増えています。
「てか」単体だとやや古く感じる人もいるようです。
「イタい」「アツい」

「イタい」は、「恥ずかしい」「空気が読めていない」といった意味で使われる言葉です。
SNSの普及により、「痛い人」といった表現は今でも使われることがありますが、
若者の間では「イタい」よりも「イタすぎる」や「黒歴史」といった言葉が使われることが増えています。
「アツい」は、「熱意がある」「感動的」といった意味で使われる言葉ですが、
現在の若者は「エモい」や「ガチ○○(例:ガチ感動)」といった表現を好む傾向があります。
「キレる」「ドン引き」

「キレる」は、突然怒ることを指す言葉で、1990年代から2000年代にかけて広まりました
。しかし、最近では「ブチギレ」や「ガチギレ」のような形で使われることが多く、単に「キレる」と言うと少し古く感じる人もいるようです。
「ドン引き」は、「相手の言動に驚いて引いてしまう」という意味で使われます。
今でも日常会話で使われることがありますが、若者の間では「それな」「普通に無理」「やばすぎ」といった表現のほうがよく使われるようになっています。
「ダサい」「ウザい」

「ダサい」は、「センスが悪い」「かっこ悪い」という意味の言葉です。
1980年代から使われている言葉ですが、今でも一定の世代には使われています。
ただし、若者の間では「イモい」「ダセぇ」といった言い方が主流になってきています。
「ウザい」は、「うるさい」「面倒くさい」といった意味で使われます。
現在も使われることはありますが、「ウザい」よりも「キモい」「だるい」といった言葉のほうが若者の間ではよく使われる傾向があります。
若者に死語を使うとどうなる?通じない理由とリアクション
意味がわからずスルーされる

死語は、若者にとっては「知らない言葉」であるため、特にリアクションをされることなくスルーされることがあります。
思わず「古っ!」と言われる

流行語は、その時代を象徴する言葉でもあるため、昔の言葉を使うと「古い」と思われることが多いです。
逆に面白がられて流行ることもある

一部の死語は、逆に「レトロで面白い」と受け取られ、若者の間で流行することもあります。例えば、「チョベリグ」などは、一部のSNSで再び注目されることがありました。
「おじさん構文」と思われる
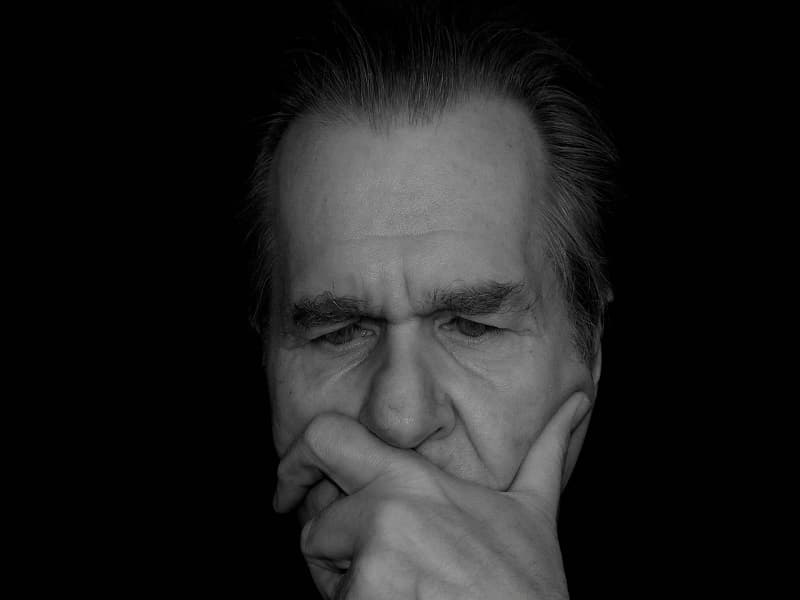
古い言葉を使うと、「おじさん構文」として若者に認識されることがあります。
「バイビー」「バッチグー」などを使うと、若者には違和感を与えてしまうかもしれません。
懐かしの死語を復活させることは可能か?
リバイバルブームで復活する可能性がある

ファッションや音楽と同じように、言葉にもリバイバルブームがあります。
たとえば、1990年代の「ギャル文化」が再評価される中で、「チョベリグ」「バッチグー」などの言葉が一部の若者の間で再び使われるようになりました。

バッチグーとか、逆に新鮮だよね!
また、1980年代のレトロな雰囲気が人気になったときには、「ナウい」「イケイケ」などの言葉がネタとして使われることもあります
。過去の文化が再び注目されると、それに伴って死語が復活することがあるのです。
SNSやYouTubeで流行ることもある

現代の若者文化の中心には、Twitter(X)、Instagram、TikTok、YouTubeなどのSNSがあります。
こうしたプラットフォームでは、意外な形で死語が流行することがあります。

死語の逆襲とかSNSマジで侮れない!
たとえば、有名なYouTuberやインフルエンサーがあえて「チョベリバ」や「アツい」などの古い言葉を使い、面白おかしく紹介することで、若い世代の間に広まるケースがあります。
TikTokでは、過去の流行語をテーマにした動画がバズることも珍しくありません。
一部の言葉は形を変えて生き残ることもある

死語の中には、完全に消えてしまうのではなく、形を変えて生き残るものもあります。
たとえば、「ヤバい」は本来「危険な」という意味でしたが、現在では「すごい」「驚いた」といったポジティブな意味でも使われています。

死語って、変身して生き続けるんだね~!
また、「ドン引き」は「ガチ引き」、「ウザい」は「だるい」といった形で言い換えられることもあります。
言葉のニュアンスが変わりながらも、同じ意味を持つ表現として残っていくケースは多いです。
使い方次第で新しい意味が生まれることもある
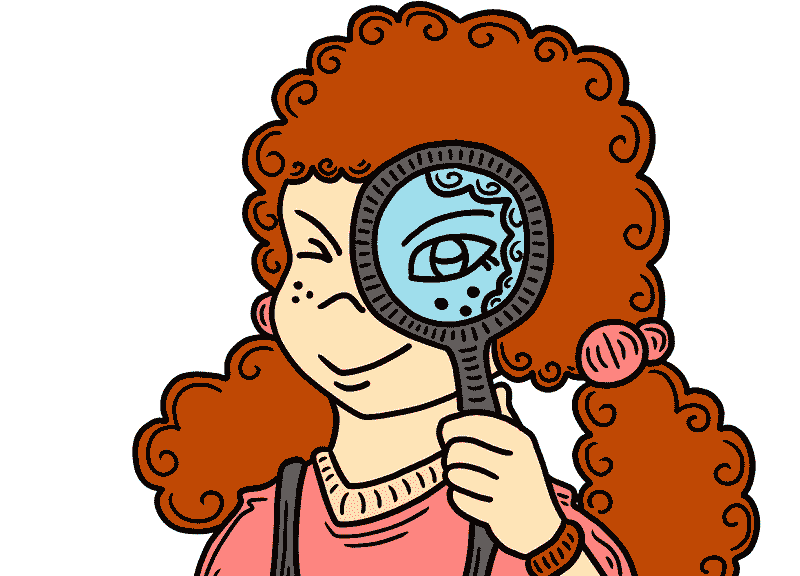
言葉は時代とともに変化し、新しい意味を持つこともあります。
たとえば、「エモい」は元々「感情的な」「感傷的な」という意味でしたが、

言葉の変化って面白いね、今の「エモい」最高!
今では「雰囲気が良い」「懐かしい」といった意味で使われることが増えています。
同じように、過去の流行語も新しいシチュエーションやニュアンスで使われることで、新たな意味を持ち、再び定着する可能性があります。
まとめ:40代がよく使った懐かしの死語と若者に通じない現状

時代の流れとともに、言葉のトレンドも変化していきます。かつて流行した言葉も、今では「死語」となり、若者には通じないものが増えました。
しかし、一部の言葉はリバイバルブームによって復活することもあります。今後、どのような言葉が再び脚光を浴びるのか、興味深いところです。